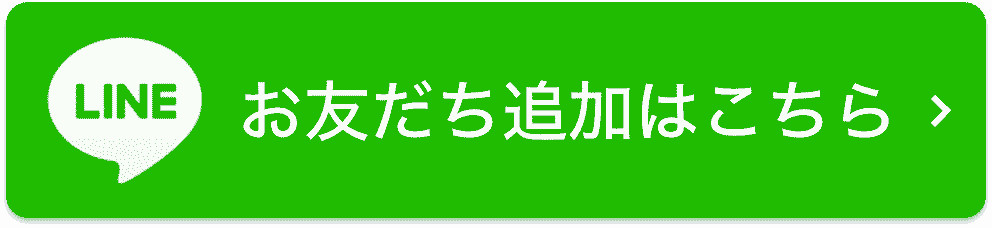神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)

神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)(Neuroparalytic Keratitis, Neurotrophic keratitis)とは、神経障害によって角膜の感覚が失われ、角膜損傷を引き起こす眼疾患です。
推定有病率は1万人に5人未満(0.05%)と非常に稀な病気ではありますが、進行すると角膜潰瘍や角膜穿孔が起こって視力が低下したり、最悪の場合は失明したりする可能性もあるため注意が必要です1)。
この記事では、神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)の症状や原因、治療方法について詳しく解説します。
この記事の著者

名前 / Name
高田 尚忠(たかだ なおただ)
高田眼科 院長|ひとみ眼科 / フラミンゴ美容クリニック 眼瞼手術担当医師
岡山大学医学部卒業後、郡山医療生活協同組合 桑野協立病院などの様々な医療機関を勤務し、現在は高田眼科の院長を務める。2022年3月より、名古屋市内の伏見駅近くのフラミンゴ眼瞼・美容クリニックを開院。
神経麻痺性角膜炎のステージ分類
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)には、3つのステージ分類が存在します1)。
| ステージ分類 | 状態 |
|---|---|
| Stage1 (軽度) | 角膜上皮の乾燥や濁り、点状表層角膜炎や角膜浮腫が特徴です。 長期間にわたってこの状態が続くと血管新生や角膜瘢痕が起こる可能性もあります。 |
| Stage2 (中等度) | 角膜上皮欠損の治癒遅延(遷延性角膜上皮欠損と呼びます)、角膜腫脹が認められます。 欠損部の縁はなめらかで隆起している状態です。 |
| Stage3 (重度) | 角膜潰瘍が特徴で、角膜穿孔や角膜実質融解に進行する場合があります。 また、稀に前房蓄膿が起こります。 |
Stage1でみられる点状表層角膜炎は、角膜上皮の最上層が点状に欠損した状態を指します。
Stage1とStage2は角膜上皮の変化や欠損にとどまりますが、重度のStage3になると角膜実質や角膜内皮にまで影響が及ぶようになり、視力へ与える影響も大きいです。
角膜上皮には再生能力がありますが、角膜内皮には再生能力がありません。
ただし、神経麻痺性角膜炎では角膜上皮もなかなか再生しないような状態になっていて、長期間にわたって同じ状況が続くと角膜に血管が侵入してきたり、傷跡が残ってしまったりします。
そのため、軽度のStage1であっても油断できません。

神経麻痺性角膜炎の症状
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)では、目の痛みが現れることはめったにありません。
ただ、進行すると角膜上皮欠損の治癒遅延、角膜実質の瘢痕形成や浮腫によって視界のぼやけが現れる可能性があります。
- 角膜知覚の低下
- 目の乾燥
- 角膜の障害による視力の低下
角膜知覚の低下
三叉神経(さんさしんけい)の障害による角膜知覚の低下は、神経麻痺性角膜炎の代表的な症状です。
目にゴミが入ったときや角膜に傷がついているときに異物感があったり痛みを感じたりするのは、三叉神経があるためです。
神経麻痺性角膜炎では、目の異物感や痛みなどの症状が現れにくく、角膜障害が進行していても気づきにくい特徴があります。
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 角膜知覚低下 | 三叉神経の障害によって角膜の感覚が鈍くなる |
| 異物感の欠如 | 角膜に傷がついても痛みを感じにくい |
目の乾燥

角膜知覚の低下が起きた結果、瞬目反射(まばたき)が減少します。瞬目反射が減少すると涙液分泌も低下してしまいますので、角膜の乾燥が進行します。
目の乾燥(いわゆるドライアイの状態)は、角膜や結膜の細胞に障害が起こる原因となるため注意が必要です。
純粋なドライアイの人は目の異物感や痛みが現れて来院する人も多いですが、神経麻痺性角膜炎では自覚症状がないので来院するタイミングが遅れてしまいやすい点が厄介といえます。
角膜上皮障害
角膜知覚の低下により、角膜上皮のターンオーバー(代謝)が障害されて角膜上皮障害を生じます。
上皮障害が持続すると角膜が濁り、視力が変化するケースもあります。主な自覚症状は視界のぼやけやかすみ目、視力低下です。
角膜潰瘍と角膜穿孔
角膜上皮障害が長引く(遷延化する)と、角膜実質までに炎症が波及して角膜潰瘍や角膜穿孔が起こるケースがみられます。
また、稀ではありますが、角膜と虹彩の間にある前房に膿が溜まる「前房蓄膿」が認められる例もあります。
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 角膜潰瘍 | 角膜上皮から角膜実質に及ぶ欠損が起こる |
| 角膜穿孔 | 角膜潰瘍が進行して角膜全層に孔(穴)があいた状態になる |
| 前房蓄膿(ぜんぼうちくのう) | 前房に好中球が沈殿して下方に溜まる |
その他の症状
その他の症状として、羞明や血管新生が現れる場合があります。
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 羞明(しゅうめい) | 光を異常にまぶしく感じる症状 |
| 血管新生 | 本来は血管のない角膜に血管が侵入してくる現象 |
神経麻痺性角膜炎の原因
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)は、主に三叉神経の機能低下や障害が原因で発症する角膜の疾患です。
三叉神経の役割
三叉神経は、顔の感覚(痛覚、触覚、温覚、冷覚など)を脳に伝える役割をする大切な神経で、おでこから眼球までの第1枝、下まぶたから頬や上唇までの第2枝、下唇から下顎や下の歯茎までの第3枝に分かれています。
目に関係する第1枝は角膜感覚を脳に伝えたり角膜に栄養因子を供給したりしていて、眼表面の健康維持に欠くことのできない存在となっています2)。
| 三叉神経(第1枝)の機能 | 役割 |
|---|---|
| 角膜の感覚 | 異物や乾燥を感知 |
| 瞬目(まばたき)反射 | 眼表面を保護 |
| 涙液分泌の調節 | 角膜の潤いを維持 |
| 栄養供給 | 角膜に栄養因子を届ける |
三叉神経障害の原因

三叉神経の障害はさまざまな要因によって引き起こされますが、神経麻痺性角膜炎の一般的な原因は感染症(とくに帯状疱疹)です。
ただ、レーシックや三叉神経痛の手術、酸やアルカリによる目の化学的損傷、点眼薬の慢性使用、全身疾患などが原因となる人もいます。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 感染症 | ウイルス(帯状疱疹ウイルス、単純ヘルペスなど)、細菌 |
| 外傷や手術による損傷 | レーシックや三叉神経痛の外科手術、化学的損傷、コンタクトレンズの長期使用など |
| 薬の使用 | 塩化ベンザルコニウム(点眼薬の防腐剤)、内服薬(抗精神病薬、抗ヒスタミン薬、抗てんかん薬など) |
| 中枢神経系の疾患 | 脳腫瘍、脳卒中など |
| 全身疾患 | 糖尿病、多発性硬化症、ビタミンA欠乏症、ハンセン病など |
神経麻痺性角膜炎の検査・チェック方法
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)の検査では、角膜知覚テストや角膜病変の検査、原因疾患の特定などを行います。
| 検査方法 | 目的 |
|---|---|
| 角膜知覚テスト | 角膜知覚が低下しているか否かを調べる |
| 角膜病変の検査 | 角膜の病変や血管新生、涙液層の崩壊時間を測定する |
| 原因疾患の特定 | 三叉神経障害を引き起こしている原因疾患を特定する |
角膜知覚テスト
角膜知覚が低下しているか否かを調べるために、角膜知覚テストが実施されます。先を細くした綿花で角膜を刺激して、角膜の知覚を調べる検査です。
神経麻痺性角膜炎では、知覚の低下または欠如が認められます。
角膜病変の検査
神経麻痺性角膜炎では、角膜上皮欠損や角膜実質の浮腫、角膜血管新生や角膜混濁などの特徴的な角膜所見が認められます。
角膜の主な検査方法は、スリットランプ検査やフルオレセイン染色です。
スリットランプ検査
スリットランプ検査は細隙灯顕微鏡検査とも呼ばれ、眼科で一般的に使用される検査機器で行います。
光の束を目に当てて、特殊な顕微鏡で目をのぞき込んで角膜や結膜などの状態を観察する検査で、角膜の病変や血管新生、混濁(濁り)などを細かく確認できます。

フルオレセイン染色
スリットランプ検査だけでははっきりしないような角膜の欠損を明確にするために行うのがフルオレセイン染色です。
フルオレセイン(染料)で目の表面を染色して、スリットランプで角膜の状態を観察します。
また、同じようにフルオレセインとスリットランプを使用して涙液層破壊時間(BUT)測定を行うケースもあります。
涙液層破壊時間(BUT)測定は、涙液の安定性(質)を評価する検査です。
神経麻痺性角膜炎の人では、涙液の質が低下して涙液層の崩壊時間が短くなる現象がみられます。
原因疾患の特定方法
神経麻痺性角膜炎を引き起こす原因疾患は多岐にわたるため、詳しい問診と全身の検査が必要です。
糖尿病や多発性硬化症などの疾患がある、点眼薬を慢性的に使用している、目の手術を行った経験がある人は医師に申し出るようにしてください。
| 原因となる疾患 | 検査項目 |
|---|---|
| 三叉神経の障害 | MRI、CT血管造影 |
| 糖尿病 | 血糖値、HbA1c |
| 帯状疱疹 | 皮膚の発疹の確認、ウイルス抗体価 |
| 脳腫瘍 | MRI、CT |
神経麻痺性角膜炎の治療方法と治療薬について
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)は難治性の眼疾患であり、対症療法しかないのが現状です。
具体的な治療方法は、重症度(ステージ)に基づいて決定されます。
欧米では、神経成長因子を含有する点眼薬(Oxervate®)が難治性の神経麻痺性角膜炎への第一選択薬になりつつありますが、日本ではまだ一般的ではありません。
| 重症度 | 治療方法 |
|---|---|
| Stage1 | 人工涙液、抗菌点眼薬 |
| Stage2 | 点眼薬、角膜の治療用コンタクトレンズ、羊膜移植 |
| Stage3 | 点眼薬の使用、角膜移植 |
Stage1に対する治療方法
神経麻痺性角膜炎Stage1の治療では、角膜の表面にある上皮細胞の再生を促す、眼の表面を保護する、といった2点が大切です。
治療は主に防腐剤を含まない人工涙液やヒアルロン酸点眼薬を用いて行います。
具体的な点眼薬として、ソフトサンティアやヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液などが処方されます。

出典:https://www.santen.com/jp/healthcare/eye/products/otc/soft_santear

出典:https://www.rohto-nitten.co.jp/medical/products/detail/?id=38
この他、感染防止目的でレボフロキサシンやモキシフロキサシンなどの抗菌点眼薬が処方される場合もあります。
Stage2に対する治療方法
1週間以上角膜上皮欠損が続いている状態(遷延性角膜上皮欠損)の神経麻痺性角膜炎Stage2には点眼薬や治療用コンタクトレンズが用いられ、血清点眼を使うケースもあります。
また、症状に応じて、羊膜移植によって角膜の欠損部分をカバーする治療を行うケースもあります。
点眼薬
| 点眼薬 | 効果 |
|---|---|
| ヒアルロン酸点眼薬 | 角膜にうるおいを与えて創傷治癒を促進する |
| ジクアホソルナトリウム | 涙の質や量を改善する |
| レバミピド | 涙の質を改善したり角膜上皮障害を改善したりする |
| 抗菌点眼薬 | 細菌の増殖を阻害する、細菌感染を予防する |
| 血清点眼 | 角膜にうるおいを与える、細胞の分化や増殖を促す |
治療用コンタクトレンズ
神経麻痺性角膜炎で起こる角膜上皮欠損に対して、治療用のソフトコンタクトレンズを装着していただく場合があります。
目の保護や点眼薬を長く目にとどまらせるのが目的です。基本的にコンタクトレンズの着脱は医師が行います。
羊膜移植
羊膜移植は、胎内で赤ちゃんを包んでいた膜(羊膜)を角膜に移植する手術です。
羊膜には、角膜と同じで血管がない、炎症を抑える働きがある、術後の拒絶反応が少ない、といった特徴があります。
手術には、1~2週間の一時的な期間だけ羊膜で角膜をカバーして組織の再生を促す方法、目の表面に羊膜を直接縫い付ける方法などがあります。
Stage3に対する治療方法
角膜潰瘍や角膜穿孔が起こる神経麻痺性角膜炎Stage3に対する治療は、点眼薬の使用と角膜移植です。
角膜移植には、角膜のすべての層を移植する「全層角膜移植(PKP)」と異常のある層のみを移植する「角膜パーツ移植」があります。
また、小さい角膜穿孔に対してシアノアクリレートといった生体接着剤で穿孔部を閉鎖する手術方法もあります3)。
神経麻痺性角膜炎の治療期間

神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)が治癒するまでには、通常数週間から数カ月かかります。
予後は人によって異なりますが、原因となる疾患の治療、角膜の治療が完了した後も定期的な眼科の受診が大切です。
治療期間
角膜上皮は新陳代謝が非常に活発な組織ですので、Stage1でみられる点状表層角膜炎のような軽症例では数週間で治癒する人もいます。
一方、発症から時間が経っているときや重症のときでは、数カ月以上の治療を必要とする場合も多いです。
予後
神経麻痺性角膜炎の予後は原因疾患や治療開始の時期によって大きく異なるものの、治療前に比べて視力が優位に改善するケースもみられます。
ただし、その一方で重度の視力障害に発展する例も多く存在するのが実情です4)。
| 予後良好因子 | 予後不良因子 |
|---|---|
| 早期発見・早期治療 | 治療の遅れ |
| 軽症例 | 重症例 |
| 原因疾患の治療 | 原因疾患の未治療 |
薬の副作用や治療のデメリットについて
神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)の治療にはデメリットがあり、点眼薬には副作用が存在します。
感染症のリスク
神経麻痺性角膜炎の人は角膜の感覚が低下しているので、外傷や感染のリスクが高くなります。
抗菌薬を使用すると感染症のリスクを軽減できますが、長期的な使用では耐性菌※1の出現にも注意が必要です。
※1耐性菌:特定の抗菌薬に対する耐性ができてしまい、その薬が効かなくなった菌。
長期的な視機能への影響
神経麻痺性角膜炎は、治療を行っても完治が難しい疾患です。長期的な視機能への影響が懸念されます。
そのため、定期的に眼科を受診して経過観察を行い、病状の変化に応じて治療方針を調整していく取り組みが大切です。
点眼薬の副作用
神経麻痺性角膜炎の治療では人工涙液や抗菌点眼薬などが処方されますが、一時的な目のかゆみや刺激感(しみる)、充血やまぶたの炎症などの副作用があります。
| 点眼薬 | 副作用 |
|---|---|
| ヒアルロン酸点眼薬 | 目のかゆみ、刺激感、充血、まぶたの炎症 |
| ジクアホソルナトリウム | 刺激感、目やにの増加、充血、目のかゆみや痛み |
| レバミピド | 味覚異常(苦味を感じる)、視界のぼやけ、刺激感 |
| 抗菌点眼薬 | 刺激感、目のかゆみ、充血、まぶたの炎症 |
羊膜移植・角膜移植のリスク
羊膜移植は基本的には合併症の少ない手術です。とはいえ、感染症のリスクや羊膜下出血、角膜上皮欠損の再発の可能性もゼロではありません。
角膜移植はどの層を移植するかによって拒絶反応が起こる確率が異なり、角膜パーツ移植よりも全層角膜移植のほうが拒絶反応が起きやすいです。
拒絶反応は術後3~6カ月で生じる例が多く、視力低下や光をまぶしく感じる羞明などの自覚症状が現れます。
| 手術 | デメリット |
|---|---|
| 羊膜移植 | 感染症のリスク、羊膜下出血、遷延性角膜上皮欠損 |
| 角膜移植 | 感染症のリスク、拒絶反応、乱視、出血、遷延性角膜上皮欠損 |
保険適用の有無と治療費の目安について

神経麻痺性角膜炎(神経栄養性角膜炎)の治療には健康保険が適用されるものと、そうでないものがあります。
保険適用
保険がされる治療にはヒアルロン酸や抗菌薬などの点眼薬や手術が挙げられますが、人工涙液(ソフトサンティア)は保険が適用されません。
また、幹細胞エクソソーム点眼薬、臍帯血清点眼薬、多血小板血漿(PRP)点眼薬、血清点眼などの特殊な点眼は自費治療となるため全額が自己負担です。
治療費の目安
| 治療方法 | 保険適用 | 治療費の目安(3割負担の場合) |
|---|---|---|
| 人工涙液(ソフトサンティア) | × | 150~200円程度/1本 |
| ヒアルロン酸点眼薬(ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液) | 〇 | 数十円/1本 |
| ジクアホソルナトリウム(ジクアス) | 〇 | 約200円/1本 |
| レバミピド(ムコスタ) | 〇 | 約10円/1本 |
| 抗菌点眼薬 | 〇 | 数百円/1本(点眼薬の種類による) |
| 羊膜移植 | 〇 | 35,000~40,000円 |
| 角膜移植 | 〇 | 160,000~200,000円 |
| 特殊な点眼(幹細胞エクソソーム点眼薬、血清点眼など) | × | 医療機関により異なる |
ただし、上記はあくまでも目安です。詳しい費用は各医療機関にお問い合わせください。
参考文献
1) MackieIE. Neuroparalytic keratitis. In: Fraunfelder F, Roy FH, Meyer SM, eds. Current eye treatments. WB Saunders; 1995: 452-454.
2) Müller LJ, Marfurt CF, Kruse F, Tervo TM. Corneal nerves: structure, contents and function. Exp Eye Res. 2003;76:521–542.
3) 永田有司, 小島良平, 木下雄人, 森洋斉, 岩崎琢也, 宮田和典. 角膜穿孔の閉鎖にシアノアクリレートが有効であった4例. 眼科手術(日本眼科手術学会誌)33: 42, 2019.
4) 山口剛史, 笠松広嗣, 松前洋, 谷口紫, 平山雅敏, 冨田大輔, 福井正樹, 島﨑潤. 神経麻痺性角膜症の臨床像と治療予後. 日本眼科学会雑誌, 127: 26-31, 2023.
SAAD, Sami, et al. Neurotrophic keratitis: frequency, etiologies, clinical management and outcomes. The ocular surface, 2020, 18.2: 231-236.
SACCHETTI, Marta; LAMBIASE, Alessandro. Diagnosis and management of neurotrophic keratitis. Clinical ophthalmology, 2014, 571-579.
MASTROPASQUA, Leonardo, et al. Understanding the pathogenesis of neurotrophic keratitis: the role of corneal nerves. Journal of cellular physiology, 2017, 232.4: 717-724.
SEMERARO, Francesco, et al. Neurotrophic keratitis. Ophthalmologica, 2014, 231.4: 191-197.
BONINI, Stefano, et al. Neurotrophic keratitis. Eye, 2003, 17.8: 989-995.
VERSURA, Piera, et al. Neurotrophic keratitis: current challenges and future prospects. Eye and brain, 2018, 37-45.
DAVIS, Elizabeth A.; DOHLMAN, Claes H. Neurotrophic keratitis. International ophthalmology clinics, 2001, 41.1: 1-11.