眼瞼下垂手術後のトラブルで失敗・後悔しないために、手術を受ける前に「必ず!!」知っておくべきこと

2026年1月16日 修正・更新
眼瞼下垂症は、以前は、一般的に知られていないマイナーな疾患でした。
様々なテレビなどで特集されたりすることで、世間で認知されるようになり、時間が経つにつれて、手術を受けられる方が日々増えている実感があります。
さて、日本において、果たして、どれぐらい多くの方が手術を受けられているのでしょうか??
今回は、厚生労働省が発表した最新の「令和6年(2024年)社会医療診療行為別統計(8月審査分)」のデータを独自に分析してみました。
結果は、1ヶ月で約5,500件! 実は身近な「眼瞼下垂手術」!!
まず驚くべきは手術の件数です。
今回のデータ(2024年6月診療分相当)によると、全国の診療所だけで1ヶ月間に約5,537件もの眼瞼下垂手術が行われています。
単純計算で年間6万件以上となります。
これは、眼瞼下垂手術がもはや「特別な手術」ではなく、白内障手術などと同様に、生活の質(QOL)を上げるための一般的な治療として定着していることを示しています。
※このデータは「診療所(クリニック)」の集計であり、大学病院や総合病院の件数は含まれていません。実際にはさらに多くの手術が行われていることになります。
結果として、片眼だけの手術をされる方もいらっしゃるとは思いますが、両眼手術を受けられるのが基本だと考えますので、概ね2,500人以上の方が日本では、毎月、全国のクリニック(診療所)で手術を受けられていることとなります。
一方で、保険外手術(自由診療手術)、いわゆる美容外科手術として、二重埋没法や二重切開手術として眼瞼手術(大半が切開をしない埋没法だと思われますが・・・)を受けられる方は、正確に統計を取ることはできませんが、少なくとも年間10万人以上と言われております。
そんなメジャーになりつつある眼瞼下垂症の手術ですが、実際手術を受けるにあたっての注意点の情報が少ないように思います。
そこでこのコラムでは、眼瞼下垂の手術時の痛みや、術後のリスクについて、そして術後にどのようにすれば快適に過ごせるかを解説します。
眼瞼下垂の手術を受けたいと思われている方は、参考になさってください。

今回の統計上の診療科別の眼瞼下垂症手術のシェアは以下の通りです。
- 眼科:約56%(3,128件)
- 外科(形成外科含む):約30%(1,657件)
- 皮膚科:約9%(483件)
保険診療の眼瞼下垂症手術は、過半数は眼科で行われています。
患者さんが眼瞼下垂手術を受ける前において知っておくべきこと
眼瞼下垂症手術を受けると、どんな経過・変化が予想されるの?
保険診療で行われる眼瞼下垂手術の第一の目的は、まぶたの開きを改善し、視野や眼精疲労などの視機能障害を回復させることです。
これは単なる見た目の問題ではなく、日常生活の質に直結する、医学的に重要な治療です。
当院では、この「機能回復」という本来の目的を最も重視しながらも、その過程で可能な限り自然な見た目になるよう、審美的な側面にも十分に配慮しています。
一部の美容外科や形成外科では、「保険診療の眼瞼下垂手術は仕上がりが悪く、不自然になる」「汚くなる」といった表現で不安を煽り、高額な自費診療へ誘導するケースが見られます。
しかしながら、保険診療であっても、専門性の高い医師が適切な診断と手術を行えば、十分に自然で違和感の少ない仕上がりが可能です。

ここで重要なのは、「審美的な配慮」とは何か、という点です。
保険診療における審美的配慮とは、「大きく変えること」ではなく、「余計な変化を加えないこと」、そして「仕上がりのばらつきを最小限に抑えること」だと当院では考えています。
美容手術では、より大きな変化を求めるほど、皮膚を切開し、切除し、縫合し、注入するといった人為的な操作が増えていきます。
つまり、変化を強く求めれば求めるほど、より人工的に、つまりは、不自然さや合併症のリスクが高まるというジレンマが常に存在します。
その点、保険診療の眼瞼下垂手術は、「機能回復」が主目的です。審美的な変化を積極的に追求する治療ではありません。
だからこそ、必要最小限の操作で、眼瞼挙筋機能の改善という本質的な問題だけに集中し、その他の要因による余計な変化を極力起こさない――この“引き算の手術”こそが、結果として最も自然で、安全性の高い仕上がりにつながると考えています。
保険診療の眼瞼下垂手術は、美容手術の「簡易版」や「劣化版」ではありません。
むしろ、手術内容において、医学的に本質的な問題の解決に絞り込み、余計な操作を排除することで、リスクを最小限に抑え、安定した結果を得ることができる、極めて合理的で優れた治療です。
✔ 見た目を大きく変えず、機能だけを治したい方
→ 引き算の手術(保険診療)
✔ 費用よりも仕上がりの完成度を重視したい方
→ こだわりの手術(自由診療の眼瞼下垂手術、美容手術)

「大きく変える」ことが必ずしも「良い治療」ではありません。
必要なことだけを、必要な分だけ行う。
それこそが、保険診療としての眼瞼下垂手術の価値であり、本当の意味での“審美的配慮”であると考えています。
それでも、保険診療の手術であっても眼瞼下垂手術は、顔の中でも重要なパーツである瞼という繊細な目の一部を変化させる手術ですので、様々な術後の変化が起こります。
手術後に予期せぬ不都合なことが起こったとしても、慌てないように患者さま側には覚悟が必要で、そして、我々手術する側(術者)からも、しっかりとした配慮、つまりはカウンセリングが必要です。
例えば、眼瞼下垂手術は瞼を開きやすくする手術という言い方ができる一方で、逆に言えば、開きやすくなった分、瞼を閉じにくくする手術だという言い方もできます。
それは、単純に目が大きく開けば、閉じるまでの距離(ストローク)が、伸びるわけで、閉じるまでの瞼の閉じるための仕事量が増えた分だけ閉じにくくなることは容易に想像できることだと思います。
したがって、当院では、眼瞼下垂手術のカウンセリングの際には、眼瞼下垂手術とは目が必ず閉じにくくなる手術だと説明をさせて頂いております。
ただ、完全に目が開いたままで閉じなくなるのではなく、少しだけ閉じにくくなるということですので、誤解ないようにお願いいたします。
注意しなければならないこととして、手術直後は、閉じる時の瞼の動きのストロークが伸びることに加えて、手術直後は、また、別の理由で、一時的に一段と目が閉じにくくなります。
簡単に説明させていただくと、眼瞼下垂症手術は、眼瞼挙筋腱膜(場合によってはミュラー筋)の位置を正しい位置に戻すことです。
眼瞼挙筋腱膜は、瞼の皮膚から見て眼輪筋の奥にあるので、眼瞼下垂症手術では、眼輪筋を切開、剥離し、移動させることで、眼瞼挙筋を露出させることが必要となります。
結果として、眼輪筋は、その手術操作により、大なり小なりダメージを受けるわけで、手術直後の眼輪筋の動きが一時的に悪くなり、目を閉じる力が弱くなってしまいます。
それらの機能障害が改善するには、ダメージが回復するまでの期間、いうなれば、リハビリ期間が3ヶ月〜6ヶ月程度は必要となります。

眼瞼手術直後は、眼輪筋が傷ついてしまうために、しばらく目が閉じにくくなりますが、傷が回復するにつれて、目が閉じるようになります。
プロスポーツ選手が、靭帯の手術を受けた後、リハビリメニューを数ヶ月こなしてから、戦線に復帰する姿を想像すれば、ご理解いただけると思います。
つまり、眼瞼下垂症手術直後においては、目の閉じにくさ、つまりは、軽度の兎眼(とがん)となることは、ある程度は仕方がなく、眼輪筋の機能が回復するために必要な期間(リハビリ期間)として、少なくとも3ヶ月程度の時間を見て、判断すべきだと言えます。
ちなみに、日常において自然と行っている普通の瞬き(まばたき)だけ、十分な眼輪筋のリハビリとなり、時間と共に、ほとんどのケースで目を閉じる機能が回復します。
友人の整形外科のドクターに聞くと、リハビリは術後早期から行うことが大事で、長期間、時間が経つと固くなってしまい、機能障害の期間が長くかかってしまいます。
手術の良し悪しは、術後のリハビリ内容に影響されるとも・・・・。
したがって、術後間もないときから、目を閉じる練習は、ある程度、意識的に行うことが推奨される場合もありますが、その可否については、主治医とのご相談が必要と考えます。
このように、眼瞼下垂手術を受けるにあたって、術後に後悔・誤解されないように、手術前に理解すべきこと(もしくは、手術後に不安に思った際に確認すべきこと)を述べさせていただきたいと思います。
眼瞼下垂症手術後のデザインの崩れ

眼瞼下垂症手術の成功率において、手術のスピードと丁寧さ、正確さが非常に重要なファクターです。
つまりは、術者の技量と手術の選択が一番、重要なことです。
だからこそ、誰に手術をして貰うのか?という意味で、ドクター選びが大事になります。
眼瞼下垂症は、視野を広げるという機能的な改善を目的となりますが、やはり、顔の手術となりますので、術後のデザイン、つまりは、先ほど述べたように審美的な要素も非常に大事になります。
当院では、術中に完成させたデザインが、最終的な手術後の仕上がりのデザインの目安となると考えるしか無いと考えております。
つまり、手術中に一旦、完成し確認した手術中のデザインが、手術の腫れ等が落ち着いた最終的な仕上がりのデザインに近いと考えることです。
当然、手術に不慣れだったりして、適当で雑な手術手技を行っていると、この法則通りにはいきません。
そのため、当院では、術中のデザインが、最大限手術の結果にマッチしたシュミレーションとなるように工夫を重ねております。
眼瞼下垂症手術では、術後の左右差が問題になることが多いと言えます。
以下の記事で詳しく説明をしておりますので参照してみてください。

先ほど、術中に確定させてデザインが、最終的な瞼の完成形になるという考え方をご提示しました。
そうであるにもかかわらず、残念ながら、手術中に眼の開きの左右差がなく、適切な形であったにもかかわらず、術後に左右差が出てしまったり、三角目(テント)になったりしていることが僅かながらあります。
ただ、手術の回復期において、一旦、デザインが崩れたとしても、ダウンタイム終盤には問題なく落ち着いてしまうことも多く経験しますので、判断が難しいとも言えますが・・・・。
手術の結果に、デザイン的な問題が出た場合には、どのタイミングで、どのように対応するべきなのか?
先ず、通常、明らかに酷い過矯正の場合には、手術後、可及的速かに行います。
少しの低矯正や瞼の歪みやボリュームの問題であれば、落ち着くのを待ってから3ヶ月以降に修正手術を行うことになります。
なぜ、再手術に踏み切る時期が異なるのかを説明していきたいと思います。
明らかな過矯正の場合
酷い過矯正の場合には、早めの修正が肝要となります。
理由としては、術後時間が経ってしまった場合の過矯正を修正する場合には、過矯正の原因となっている瘢痕組織を全て外す必要があります。
瘢痕組織を完全に取り除くことは、実は、非常に難しいがために、時間が経ってしまった過矯正修正手術の成功率が著しく下がる要素となります。
したがって、激しい過矯正の場合には、瘢痕形成が起こる前に、出来るだけ早期に修正手術を行う方が成功率が高くなると言えます。
しかし、不用意に再手術を行なってしまうと、逆に、瘢痕組織だけを増やしてしまい、余計に修正が難しくなるという一面もあります。
再手術は過矯正であっても、傷口が落ち着くのを待って、半年以上待ってから行うと説明されている医療機関がありますが・・・ミュラー筋に操作を加えている場合には間違ったことだと考えております。
当院では、眼瞼挙筋前転法で行っているため、術後の癒着等のリスクが、ミュラー筋タッキング等とは異なり少ないと言えます。
加えて、出来るだけ、組織への侵襲を抑えるようにしているため、結果として、瘢痕形成が少ないため、修正手術になったとしても、修正が容易だと考えております。
したがって、明らかな過度な過矯正の場合には、手術翌日に修正を行うこともありえますが、当院では、ほぼありません。
少し過矯正の状態の場合
多少の過矯正の場合には、3ヶ月程度は待った上で、きちんと結果を見てから修正手術を行うことが殆どです。
手術直後は、目を見開こうとする癖が強い場合もあり、慣れていないことで、力の入れ具合の問題で、多少の過矯正になってしまうことがあり、時間と共に、改善することも多いといえます。
現在、主流になつつあるミュラー筋に操作を加える手術方法の場合は、ミュラー筋が非常に脆弱な筋肉組織であり、腱組織と違い、瘢痕による変性・癒着を起こしやすいというがポイントとなり、過度な過矯正の場合には、早期の修正手術が望まれます。
少しの低矯正や瞼の歪みやボリュームの問題
逆に、低矯正(弱矯正)の場合には、瘢痕組織の除去の必要性がそこまでない上に、また、術後の腫れなどの影響で、一時的に瞼が下がっていることもあるため、術後の炎症が落ち着くまで待つ方が無難だと言えます。
また、二重の幅が広いケース、術後の瞼の腫れぼったさが強いケースなども、単純に腫れていることで起こっていることが多いので、腫れが落ち着くまで待つことが最適解だと考えます。
再手術の判断についてのまとめ
結論として、手術方法により対応が変わりますが、明らかな過矯正が確定したのであれば、可及的に速やかに、低矯正の場合には、経過をしっかり追ってから(術後3ヶ月以降が目安)、再手術を行うことになりますが、手術の瘢痕形成の状態によっては、早く行ったほうが良い場合があります。
再手術になってしまうことは非常に残念なことですので、可能な限り避けなければならない事象です。
当院でも、術前説明、カウンセリングで、必ず説明するようにしているのが、再手術のリスクについてのお話です。
どんなに素晴らしい腕を持つ眼形成外科医の名医でも、再手術(リオぺ)のリスクは、避けられません。
再手術という結果になったら、直ぐに失敗という結論になるという考え方をしがちですが、再手術を行うことで、リカバリーさえ出来れば、一連の流れの手術として、上手くいったと考える事も出来るのではないでしょうか?
したがって、やり直し手術が難しくならないように、初回手術から配慮した手術方法の選択・工夫を重ねた手術操作が非常に大事だとも考えてます。
具体的には、瘢痕を出来るだけ作らないように、瘢痕組織が問題を起こさないようにすることが重要となります。
そのためにも、手術方法は、眼瞼挙筋前転術が前提であり、加えるなら、高周波メスを使用したり、瞼板固定の埋没糸の糸の素材、固定方法を工夫したり、手術操作が最小になるように手術時間を短くなるように工夫したりを積み重ねているのが当院の眼瞼下垂手術です。
眼瞼下垂手術の名医とは、常に最悪の状況(再手術)に備えて、最大限の備えをしているところだと思っております。、
眼瞼下垂症術後の二重デザインの問題
当院を含め、さまざまな医療機関では、二重の幅については、原則、保険診療で行う場合には、ご本人のご希望に添えて反映することは行っておりません。
保険診療の眼瞼下垂症手術は、美容手術ではなく、瞼を開きやすくするための機能回復の手術であるからです。
例えば、当院での保険診療手術後における二重幅については、眼瞼下垂症術による結果的な変化であり、こうなるだろうという予想を含めて、結果をお示ししておりません。
できるだけ、手術によって、審美的な変化が少なくなるようにするというコンセプトで行っております。
そのため、保険診療での眼瞼下垂症手術では、皮膚切除は2、3mm程度と綺麗な術野を作るの必要な最低限度としております。
結果として、眼輪筋切除も最小限であり、眼窩脂肪も除去も行いませんし、シンプルに眼瞼下垂を改善させる手技、つまりは、引き算の手術として完成された手術手技だと自信を持っております。
通常、腱膜性眼瞼下垂症は、その病態から、二重幅が広くなるという特徴がありますので、腱膜性の眼瞼下垂症を手術で改善させると、狭くなります。
加えて、眼瞼下垂症手術後は、術後眉毛下垂が起こりますので、皮膚被りが増えるということになります。
つまり、やや狭目の二重幅になることが多いと思っていますが、瞼の状況によっては、奥二重になることも、広めの二重幅になることもあります。
さらに言えば、蒙古襞の状態によっては、末広型の二重にも、並行型の二重にもなります。

歳を重ねると、蒙古襞がなくなっていきます。
蒙古襞がない方、つまり、高齢者の方は、二重は平行型になりやすいと言えます。
保険診療での眼瞼下垂症手術は、二重幅を作ることを目的とする手術(重瞼術)ではなく、あくまで眼瞼下垂症の治療で行う、機能改善を主となるものです。
美容外科等において自由診療で行う二重手術(埋没法、二重切開手術)では、当然、二重瞼にすることを目的として手術を行うものです。
つまりは、美容手術は、変化に価値がある手術として行っているわけです。
言い換えれば、必ず、二重瞼にしなければならないという前提があるため、広めのガッチリとした二重瞼のデザインにすることが多いと言えます。
当院としては、実は、日本人において、広すぎる二重は問題になりやすいと考えております。
私自身、他院修正手術を含めて、1万人を軽く超える患者様に対して眼瞼下垂症手術を手がけてきた経験上、二重幅は広ければ広いほど、不自然さが出てくると考えております。
つまり、もともと、欧米人とは違い、日本人は一重瞼の方が多いですので、狭ければ
もちろん、日本人の中にも、欧米人に似た作りの方もいらっしゃいますので、その場合には、少し広めの二重にした方が良い場合もあります。
蒙古襞の有無によっても、少し広めの平行型二重になることもあります。
そういった意味で、私どもの自然だという認識と、
二重の幅などを含めて仕上がりの結果に関しては、シュミュレーションを行ったりして、術前に保証するものではなく、あくまで、手術中に仕上がったときにご本人(可能であれば家族にも)に実際に確認していただくことで担保しております。
軽度の眼瞼下垂(もしくは、眼瞼下垂ですらないケース)の場合、美容目的として、眼瞼下垂手術を受けに来られる方がいらっしゃいます。
そうしたケースは、審美的なご希望が強く、ご自身が希望するデザインになることを希望されることが多いとも言えます。

眼瞼下垂症手術の保険適応の条件として、眼瞼下垂の程度出るか
切開線の位置だけでなく、皮膚の伸展性や余剰量、二重の癒着の深さ、眉毛の高さの変化や目の開きに伴う眼瞼挙筋の二重の引き込み具合、蒙古襞の有無といった多くの要素が複雑に絡みあって、二重の幅は決まってきます。
そのため、これらの複数の要素の1つでも左右にズレが生じますと、術中にデザインした形に予定した通りの二重の幅にならないことも多くあります。
したがって、術前に、二重幅をどの程度のものにするのか?というゴールを設定されてしまうと、術中に、複数の要素の微調整の対応が必要となり、手術の難易度が飛躍的に高くなってしまいます。
そういうこともあり、保険診療での眼瞼下垂症手術では、シュミュレーションなどを行ったりして、希望の二重に合わせることを約束して手術を行うことはありません。
逆に、手術の中で、二重幅などに配慮しないということは、術中の余計な調整作業がなくなりますので、見た目が不自然になる可能性が減り、その瞼にあった自然な二重になるとも考えることができます。

美容手術あるあるですが、美容手術を重ねれば重ねるほど、ナチュラルさがなくなり、人工的に不自然な仕上がりになってしまいます。
だからこそ、当院では、保険診療の眼瞼下垂症において、機能回復にのみスポットを当てて、シンプルに、余計なことをしないことで手術することで、結果的に、ナチュラルな仕上がりになるのではないか?と考えております。
つまりは、術後トラブルが少ないとも言えます。
当院は、高品質の結果を求めた眼瞼下垂症手術を行うことを目標に、日々研究してきました。
高品質であるためには、①そもそもが完成度が低い ②結果がバラついている の可能性を如何に減らすか?だと考えております。
つまり、当院では、眼瞼下垂症手術にオリジナルの手術レシピを作り、それをどんどんシンプル化することで、手術結果がバラつかず、常に、安定した結果が出るようにコントロールしているイメージです。
例えていうならば、パティシエのお菓子作りのコツが、常に、レシピを大事にして、そのレシピを厳守して作ることと似ております。
具体的には、皮膚切開線、皮膚切除量、眼輪筋の削り方、眼窩脂肪の除去の有無、挙筋腱膜の前転固定の位置などの基準をレシピとして・・・決めているわけです。
ここで、眼瞼下垂手術で、問題となる二重トラブルについて、まとめたいと思います。
| 予定外重瞼線 | 二重のラインが三重になる・元のラインが出現する・切開線とは違う場所にラインが出来る可能性があります。術前からサンケンアイ、三重瞼だったり、皮膚切除が足らなかった場合に発生しやすいと考えます。 |
| 目頭側・目尻側のラインが二股になる | 目頭・目尻側のラインが二股に分かれ、綺麗な一本のラインにならないことがあります。創部、つまり傷跡が硬い時の起こることがあります。 |
| ラインが浅い | 切開線の傷口とまぶたの筋肉の癒着組織が剥がれて弱くなりますと、ラインの食い込みが浅くなってしまいます。術後に傷を傷を触ったり、引っ張ったりしていることで起こることが多いと言えます。 |
| 二重のラインが短い | 二重の幅を広くしたり、タルミを切り取ったりしますと、二重の上に被さる皮膚が少なくなりますので、二重の折れ込みが浅くなり、目頭や目尻の二重の長さが短くなる。 |
| キズアトが気になる | 切開した傷が凹んだり、糸の跡によって、傷が一直線ではなく細かくジグザグ見えるようになったりすることがあります。治癒過程で傷口が開いた場合に起こりやすいです。 |
| 二重の食い込みが深すぎる | 切開法で作った二重のラインは、ラインが消えないように傷口をしっかり溝になるように縫合し、癒着を作くるため、術後早期では食い込みが深くなります。4~6ヶ月経過してむくみが落ち着き、傷跡がやわらかくなりますと、通常、食い込みは浅くなってきます。 |
| 二重幅が広すぎる | 二重を規定する切開線の位置の設定が広すぎており、また、皮膚切除量が多いとなりやすいと言えます。 |
| 左右差がある | 術前から左右差がある場合には、瞼の構造に致命的な左右差(瞼のボリューム、眼瞼挙筋の筋力の差など)があったりすると、起こり易いと言えます。 |
このように、眼瞼下垂手術による二重の形に関するトラブルは、意外に多岐にわたります。
実は、二重幅を狭めに設定することで、上記のような二重トラブルになる可能性を減らし、かつ、なったとしてもリカバリーをしやすく出来ると言えます。
その理由を説明をしますと、先ず、二重トラブルの原因の大部分が、皮膚の切除量、切開線の設定値、二重を作るための癒着縫合の問題となります。
この中で、一番どうしようもなくなるのが、皮膚の取り過ぎです。
二重幅を確実に作ろうとしたり、広くしようとすると、通常、皮膚切除を多めにしなければなりません。
したがって、二重幅を狭くすると言うことは、皮膚の切除量を少なくすると言うことと同じですので、術後トラブルが起きた際に、余剰皮膚を取るだけと言う意味で、リカバリーがやりやすいと言うことができます。

当院の保険診療での眼瞼下垂症手術は、皮膚切除幅を3mm程度と出来るだけ少なくしております。
この量であれば、過剰切除の可能性がないと言ってよいとです。
たるみを取ること、被りを取ること、二重を作るためには、当然、より多くの皮膚切除を検討すべきですが、そういった効果を狙って行うのは、保険診療ではなく美容手術の範囲と考えております。
眼瞼下垂手術後の左右差について

眼瞼下垂症手術後に左右差が出てしまう一番の原因として、無視できないことに、元々の瞼の状態に左右差がある場合です。
人の身体は、左右対称ではないことは有名な事実だと思います。
形態的に左右差があるのも当然なのですが、例えば、手の握力にように筋力、つまりは瞼を持ち上げる力である挙筋機能にも左右差があるのが一般的です。
それは、瞼を引き上げる筋肉である眼瞼挙筋の筋力にも左右差があるということにもなります。
そして、その左右対称性は、生まれつきの部分もあるのですが、年を重ねることでも大きくなります。
眼瞼挙筋も、外的な要因、老化などで、腱膜が断裂したり、眼瞼挙筋自体が脂肪変性を起こしたりして、筋力が衰えていきます。その衰えは左右均等ではないことが多く、結果として、目の開きに左右差が生まれます。
例えば、眼瞼挙筋の筋力に差があると、筋力の弱い方は、幾ら、手術で腱膜の位置を調整しても上がりが悪く、眼瞼挙筋の状態の良い方は、逆に、ちょっとした手術操作で上がり易いため、結果として左右差となり易いと言えます。
つまり、左右差ない状態を確認して手術を終えたとしても、極端に眼瞼挙筋機能の左右差がある場合、術後、弱い方が下がって、左右差になることもあります。

術前から左右差がある症例では、術中のデザイン確認時に、全く左右差のがなくなっていても、術後、左右差が出てしまう場合があります。
特に高齢者の方は、加齢性変化による挙筋機能の低下だけでなく、左右差も大きくなります。
加えて、眼輪筋、骨格、眼窩脂肪、皮膚のたるみなどにおいても左右差が増えてくることが多いため、結果として、高齢者の手術難易度は高いことがあります。
そういった手術前から左右差がある瞼に眼瞼下垂症手術をおこなったとして、手術手技では埋められない構造の場合には、どうしても、術後の左右差が生まれてしまう確率が高くなります。
片眼だけの眼瞼下垂手術後の変化

片眼のみの眼瞼下垂手術の失敗要因:ヘリング現象
先の項の話とも被るのですが、眼瞼下垂症は術前から左右差があることも一般的によくあることです。
片方が正常な開き方をしていて手術が必要ないということで、下がっている方の眼瞼だけを手術欲しいというご希望を頂くのですが・・・
その判断には、大きな落とし穴があるので、注意が必要です。
実は、片方の下がっている瞼(まぶた)に手術を行い、片方だけ瞼を開けやすくしたら、反対側の手術を行っていない方の瞼(まぶた)が手術前より下がることがあります。
この現象をは、ヘリング現象と呼ばれております。
公園にある遊具であるシーソーに似ている感じです。
このヘリング現象を考えると、手術前に左右差がある両側の眼瞼下垂では両側同時に手術を行った方が無難だと説明をしております。
その理由を説明させていただくと、片側の眼瞼下垂のみに対する治療では、手術前では、治療する方だけでなく、治療しない側の眼瞼挙筋と前頭筋も、無意識に過度に収縮して、
そして、例えば、手術により、眼瞼下垂の側のまぶた(右目)
これが、先に述べたヘリング現象であり、結局、ヘリング現象で下がってしまった
そして、今度は、左目の手術を追加すると、
当院の手術では、術中において、このヘリング現象の変化を確認しながら、慎重に左右差が無いように調整に、調整を重ねて瞼の高さを整えております。
そのことが、再手術のリスクを最大限減らす考え方、つまりは、成功率を上げることに繋がると考えております。
したがって、左右差を少なくするには、基本的には、両眼同時手術をすることが最低限、必要条件だと思っております。
そして、両眼同時の眼瞼下垂手術においても、麻酔の左右差、瞼の左右差を出来るだけ埋められるような手術操作に気をつけているのは、言うまでもありません。
しかしながら、当院では、柔軟な対応を心がけるようにしておりますので、ご本人から強く希望されれば、片眼の手術をお受けするようにしております。
ただ、片眼のみの手術を行う場合には、どうしても左右差が起こる可能性が高いことを十分に承知して頂いて、手術に臨んで頂ければと思います。
眼瞼下垂症手術で左右差になってしまう原因
さらに、片眼のみの眼瞼下垂症手術において、左右差が出てしまう原因にはいくつかありますが、大きなものとして麻酔という要素があります。
麻酔のお陰で、痛みを無くすことはできるのですが、結果として、
(もちろん、針による内出血によるボリューム変化も無視はできません。)
麻酔液で膨らめば、ボリュームが増えますので、その分、
さらに、麻酔には、筋肉の動きを麻痺させる作用があります。
結果として、術中に左右差を見ても、片目手術の場合ですと、麻酔を行っていない瞼と比較しても、参考にはならないため合わせが難しいと言えます。
両眼同時手術だったとしても同様のことが言えますので、当院の手術では、麻酔の使用量は片眼2cc程度とかなり少なくするように努力しております。
麻酔が少ないということは、麻酔の効きが浅くなるとも言え、麻酔がすぐに覚めて易いとも言えますので、手術時間を短くしないと、結果的に追加の麻酔をすることになり、より左右差が出てしまうリスクが上がると言えます。
術後の視力の変化

コンタクトレンズ、特にハードコンタクトレンズを外した直後に、眼鏡をかけたら、なんだか、見え方がボヤけたという経験はないでしょうか?
角膜というのは、透明なドーム状の形をしておりますので、実は、眼球において、非常に重要なレンズだと言えます。
その形が変わることにより、眼球自体の屈折の状態、つまりは、度数が変化します。
つまり、コンタクトレンズの圧迫により、一時的に角膜浮腫(むくみ)が起こるために,角膜の厚さ,角膜の曲率半径などの角膜の形が変化し、屈折状態が一時的に変化することをスペクタクルブラー現象と呼んでおります。
コンタクトレンズ装用者に対する眼鏡処方を行う際に、裸眼の状態で過ごしていただいて、スペクタクルブラー現象の影響を無くしてから眼鏡処方を行わなければなりません。
通常、スペクタクルブラー現象は、数十分〜数時間でなくなり、角膜の形は、元の状態に戻ります。
同じようなことは、眼瞼下垂症手術においても、角膜の形状変化というのは、考慮に入ればければならない要素だったりします。
瞼が角膜を抑える力を眼瞼圧(がんけんあつ)というのですが、眼瞼下垂手術を行うと、この眼瞼圧が変化することで、角膜の形が術前と変化する可能性があります。
近視・乱視などの眼の屈折状態が変化して、見えやすくなることもあれば、逆に、見にくくなることがあります。
しかしながら、眼瞼圧による視力の変化は、多くの眼瞼下垂手術を執刀してきた経験上、個人的には非常に少ないと考えております。
むしろ、コンタクトレンズ装用者が腱膜性眼瞼下垂になることが多いこともあり、コンタクトレンズ装用者が眼瞼下垂手術を受けると、暫くコンタクトレンズを付けられない期間が続くことになります。
結果として、コンタクトレンズの中断によって角膜の形に強く影響を及ぼしていたコンタクトレンズの圧迫の要素がなくなり、スペクタクルブラー現象がおこり、見え方が変わる可能性もあります。
眼瞼下垂症手術による眼瞼圧の変化による視力の変化ではなく、単純なコンタクトレンズによるスペクタクルブラー現象である可能性が強いです。
ただ、眼瞼下垂症を受けた方の中には、術後の視力変化を訴える患者さんが多いのは事実です。
しかしながら、眼瞼下垂症手術は、瞼を対象とした手術であって、眼球を手術するわけではないことから、術後に視力が大きく落ちると考えることはないと考えております。
視力が落ちたとしても、一過性であると言えます。
また、眼瞼下垂症手術後には、傷口に眼軟膏を塗布する形になるのですが、その眼軟膏が目の中にも入ってしまい、眼表面に軟膏成分による油膜が張ってしまうことで、ボヤけてしまい、視力低下を訴える方が多いので注意が必要です。
抜糸した後には、軟膏も中止できるので改善が見込めるので、問題がありません。
さて、白内障手術やレーシック手術などの屈折手術と眼瞼下垂手術を予定している場合、眼瞼下垂手術をまず先に行うべきなのか? それとも、屈折手術を先に行うべきなのか?の問題があります。
この疑問の答えについては、先に、屈折手術を行ってしまうと、眼瞼下垂症手術によって、視力が変わってしまうので、先に眼瞼下垂症手術を行うべきだという意見もあります。
しかしながら、白内障手術やレーシック手術などの屈折手術に限らず、眼科の手術の多くは、手術中に目をつぶってしまわないように開瞼器という手術器具を使用します。
そのため、無理な開瞼器の使用により、眼瞼挙筋腱膜を傷つけてしまい、術後眼瞼下垂症を引き起こす可能性があります。
したがって、先に、屈折手術を行った方が良いと言える一面も一概に、どちらを先にやった方が良いのかは答えがありません。

眼瞼下垂手術後に、開瞼器を使用するような手術(白内障、緑内障、硝子体手術(網膜手術))を受けられる場合には、手術をされる先生に眼瞼下垂手術後であることを伝えておいた方が良いと思います。
術後のドライアイについて

眼瞼下垂の手術を行うと、目が大きく開くようになるため、これまでよりも空気に触れる面積が増えます。
その結果、涙が蒸発しやすくなり、さらに涙を排出する「涙のポンプ機能」も改善されるため、一時的にドライアイ気味になることがあります。
また、涙は角膜の表面に広がり、「涙液レンズ」と呼ばれるレンズのような役割を果たしています。
この涙液レンズの状態が変化することも、術後のドライアイによって起こり得ます。そのため、術後には一時的に見え方(視力)の変化を感じることがあります。
当院では、術後しばらく点眼治療を行っていただくことで、多くの方が3か月前後で点眼が不要になるほど改善していきます。
つまり、術後のドライアイやそれに伴う視力変化は、多くの場合一過性のものですので、過度に心配する必要はありません。
なお、最近の臨床眼科学会では、ミュラー筋タッキング法と比較して、眼瞼挙筋腱膜前転法の方が、術後に重度のドライアイが生じやすい傾向があるという報告がありました。
当院では主に眼瞼挙筋腱膜前転法を行っていますが、その理由と同時に、なぜ術後ドライアイが起こりやすいとされるのかについても、独自の視点で分析しています。
多くの医療機関では、挙筋腱膜を折りたたんで瞼板に固定する際に、瞼板に無理な歪みが生じてしまう固定方法が行われていることがあります。この瞼板の歪みこそが、術後ドライアイの大きな原因のひとつではないかと、当院では考えています。
まばたき(瞬目)は、角膜の表面に涙を均等に広げるための大切な動作です。その際、柔軟性のある瞼板が角膜の表面に沿うように動くことで、涙はムラなく広がります。
しかし、瞼板に無理な歪みがあると、角膜との間にわずかな隙間ができてしまい、涙が均一に行き渡らなくなります。その結果、涙のムラが生じ、ドライアイを引き起こしやすくなるのです。
つまり、瞼板に糸を固定する際には、非常に繊細な配慮が必要であり、不適切な固定方法は術後ドライアイの原因になってしまいます。
当院で行っている特殊な前転固定方法では、このような瞼板の歪みが起こりにくい構造を意識しており、術後のドライアイが強く出にくいと考えています。
実際、当院で手術を受けられた多くの方は、術後早期にはドライアイを自覚されることがあっても、数か月以内に改善しているケースがほとんどです。

眼瞼下垂の手術を受けてから、目が閉じにくい、完全に閉じない

目が閉じなくなることを兎眼(とがん)と呼びます。
眼瞼下垂症手術を受けると、必ず、出現する症状と考えて手術を行っております。
つまり、「まぶたが閉じない」と言われることは、術後早期においては、大部分の患者様から聞かれる状態であり、当院としては、想定の範囲内だと考えております。
眼瞼下垂症は、目を開きやすくする手術なのですが、言い換えれば、目を閉じにくくする手術だと言えます。
したがって、手術後、腫れや目の開きが良くなることにより、目が完全に閉じない時期がでることは、当然のことであり、問題がないことが多いと言えます。
また、先の項で説明したように、術後ドライアイなどにより角膜への障害が起きることがあります。
さらに説明すると、瞼の閉眼は、無意識で行っている動作でもあるので、一旦、手術で開きやすくすると、どうしても閉じにくくなるのは、致し方がないとも言えます。
これは、海外旅行で、時差のある場所に行って起こる「時差ぼけ」と同じようなもので、手術後の状態に慣れて閉じるようになるまでは、時間が必要となります。
とくに、より無意識の状態となる睡眠時に目を開けた状態になってしまうとも言えます。
特に、術前の眼瞼挙筋機能が少ない方の場合、目の開きを良くするために、眼瞼挙筋腱膜の前転固定を強くせざるを得ないため、起こることが多いので、注意が必要です。
先天性眼瞼下垂症、腱膜性眼瞼下垂症でも挙筋が萎縮している高齢者の方など眼瞼挙筋機能が少ないケースでは、眼輪筋も弱いため起こりやすいと言えます。
眼瞼挙筋は、なかなか鍛えるのが難しいのですが、眼輪筋は、眼瞼挙筋に比べて、大きい筋肉なので、比較的鍛えるのが容易な筋肉で、術後、時間が経つことで、閉じ方が改善すると考えます。
ただし、明らかな過矯正の場合には、早期の修正手術を考慮しなければなりませんが、基本的に、3ヶ月程度様子をみて、その点は、執刀した医師の診断が必要となると考えます。
また、眼瞼下垂症手術は、身体の可動部の手術でもあります。
したがって、可動部の手術を行った場合には、動きが滑らかになるまで、リハビリ期間が必要だと考えていただいても宜しいかと思います。
眼瞼下垂症手術は、眼輪筋の奥にある眼瞼挙筋を調整する手術であるため、手術操作により、眼輪筋を傷つけてしまいます。
結果として、手術後は、眼輪筋の機能障害が起こり、目を閉じるという本来の機能が回復するまでに、リハビリが必要と言えます。
人は、1日に2万回程度の瞬目(まばたき)をしており、この自然な瞬目(まばたき)が、ちょうど良いリハビリに自然となると考えております。
そういった観点から、自然な瞼の動きが戻ってくるには、眼瞼下垂症が終わってから、3ヶ月〜6ヶ月程度のリハビリ期間が必要となると考えます。
それでも、眼輪筋の回復が思わしくない場合には、傷の状態が落ち着いてからではありますが、目をしっかり閉じる練習を意識的に頻繁に行なっていただく必要性も出てきます。
現実的に、術後、軽度の兎眼の方で、この閉眼の訓練を意識的に行うことで、術後の兎眼が回復したケースもあります。
また、普段、力を抜いているときは、問題ない開き具合なのに、ふとした瞬間に、思ったよりも目が大きく開き過ぎると言われることがあります。
つまり、手術前と同じように目を開いた時に、黒目の上の白目が見えてしまう状態(上三白眼)、ビックリしたような目になります。
3~6ヶ月程度を経過してくると、強くなった目の開きを調整するようになり、上三白眼は目立たなくなります。
眼瞼下垂手術を受けたら、手術前よりも、余計に皮膚が被った??
眼瞼下垂の手術を行ったあと、眉が下がってきて、皮膚のたるみが目立つようになることがあります。
その結果、「皮膚がかぶってきた」「二重が狭くなった」「三重になった」などの変化が起こり、追加で皮膚切除(眉下切開など)が必要になるケースもあります。
これは、決して手術の失敗ではなく、眼瞼下垂という病気の性質上、起こりうる変化です。
後天性眼瞼下垂症は、初期には気づきにくい病気です
後天性眼瞼下垂症は、発症初期には自覚症状が出にくいという特徴があります。
その理由は、加齢などによる変化で眼瞼挙筋腱膜が緩んだり外れたりする過程が、ある日突然起こるのではなく、少しずつ進行していくからです。
そのため、
・最近、目が小さくなった気がする
・眠そうに見える
・夕方になると目が重い
といった、あいまいな違和感として始まることがほとんどです。
額の筋肉が「代償」してくれるため、症状が隠れてしまいます
眼瞼下垂がある程度進行しても、額の筋肉(前頭筋)が無意識に働いて、まぶたを持ち上げようとします。
この働きによって、軽度〜中等度の眼瞼下垂症は、一見すると問題がないように見えてしまうことがあります。
このような状態を、
👉 隠れ眼瞼下垂
👉 代償期の眼瞼下垂 と呼びます。

隠れ眼瞼下垂は、簡単に見分けられます
このような代償が起きているかどうかは、以下のポイントで判断できます。
✔ 眉を上げて目を開けていないか
✔ 常におでこにシワが入っていないか
✔ リラックスすると目が開きにくくならないか
このような癖がある方は、実は眼瞼下垂が隠れているだけというケースが少なくありません。

眼瞼下垂症を専門にしていない医療機関で、眼瞼下垂症の相談をしても、隠れ眼瞼下垂症に気づかず、眼瞼下垂症を否定されてしまうことがあります。
視野が狭くなって初めて「病気」と自覚されます
前頭筋の代償能力には限界があります。
この代償が効かなくなったとき、初めて
・視野が狭い
・上が見えにくい
・まぶたが邪魔
といった、眼瞼下垂症を決定づける症状を自覚することになります。
手術後に眉が下がるのは「正常な反応」です
眼瞼下垂手術によって目の開きが改善すると、前頭筋によるバックアップが不要になります。
その結果、
👉 前頭筋の緊張が緩む
👉 眉が下がる
👉 皮膚が余る という変化が起こります。
これにより、
・奥二重になる
・皮膚がかぶる
・三重になる(予定外重瞼線)
といった状態が生じることがあります。
皮膚の切りすぎはリスクになるため、判断が非常に重要です

眼瞼挙筋前転法などの眼瞼下垂手術では、皮膚を取りすぎることが大きなリスクになります。そのため、皮膚切除量の判断は、術者にとって非常に悩ましいポイントです。
皮膚を取りすぎてしまうと、
・閉眼障害
・兎眼
・ドライアイ悪化
などのリスクが高まります。
その場合、眉下切開で対応します
術後に皮膚の余りが問題になった場合には、眉下切開によって余剰皮膚を処理することで対応できます。
これは、
✔ 見た目を整える
✔ まぶたの重さを軽減する
✔ 目の開きを安定させる
という目的があります。
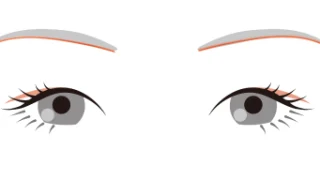
前頭筋の緊張は、術後に変化することがあります
前頭筋の緊張は、
・手術中に緩む場合
・術後しばらくしてから徐々に緩む場合
・逆に、緊張が残る場合
など、個人差が非常に大きいです。
そのため、経過観察がとても重要になります。
ボトックスが有効なケースもあります
前頭筋による代償の影響を減らすために、眼瞼下垂手術前にボトックスを注射することが勧められる場合もあります。
これは、
👉 筋肉の力を一時的に緩める
👉 本来のまぶたの状態を評価しやすくする
というメリットがあります。
また、手術後に
・目を見開きすぎている
・過矯正に見える
・無意識に眉を上げてしまう
といった場合にも、ボトックスは非常に有効です。
眼瞼下垂手術後の神経感覚の異常

眼瞼下垂症手術後に手術を受けられた方から、よく質問を受けるのは、手術した部分の感覚が無いこと、傷口のツッパリを感じることについてのことです。
眼瞼下垂症において、特に、日本人は、欧米人と違って皮膚の余剰が多いことが特徴だと言えます。
日本人、とりわけ老人性の眼瞼下垂手術においては、皮膚切除が必須とも言えるわけです。
皮膚切除をすると、どうしても皮膚の表面の知覚感覚を司る末梢神経を傷つけることは防ぎようがありません。
この末梢神経の損傷によって、眼瞼下垂症手術後は、暫くの間、瞼の触覚がなくなり、少し痺れた感じになります。
それでも、深部感覚は残るので、傷口のツッパリ感は残ります。
概ね3ヶ月〜6ヶ月ほどで、末梢神経は治癒するので、感覚の異常は無くなっていきます。
手術後に自律神経の不調を訴える方もおられます。
中には、原因不明の傷口の痛みを訴えられる方もいらっしゃいます。
この場合には、神経痛用の痛み止めや抗不安薬などの内服で対処します。
眼瞼下垂手術で、全ての肩こり・頭痛などの不定愁訴がなおるわけではない

例えば、眼瞼下垂症手術を勧めるホームページをご覧になると、必ず書かれている文句・・・手術をすると、肩こりが治る!!頭痛が治る!!眼精疲労が治る!!
確かに、眼瞼下垂症手術を受けると、多くの場合で頭痛や肩こりは改善しますが、そうでないこともあります。
それは、全ての疾患の要素は、単一の要因によって成り立っているものもあれば、複合的な要因によって成り立っているものもあるからです。
わかりやすく言えば、たしかに、眼瞼下垂症を治療することで治る肩こりもあります。
しかしながら、肩こりの原因は数十種類もあって、人によって様々なのです。
特に、「同じ姿勢、眼精疲労、運動不足、ストレス」によるもので、4大原因とされております。
また最近は、肩こりと血圧との関連性も言われており、従来は低血圧など血行不良の方に肩こりが多いとされていたのですが、逆に、高血圧の方にも多く見られます。
このように肩こりを一つとっても、原因は様々で、対処法も異なってきます。
まとめ

今回の記事は、如何だったでしょうか?
眼瞼下垂症は、眼科学的にも、もちろん、医学的にも一刻の猶予も争うような緊急性のある疾患ではありません。
また、眼瞼下垂症手術は、どんな名医が手術したとしても、大変難しい手術です。
審美的な要素と機能的な要素という二つの尺度で合格点を出さなければなりません。もちろん、両眼のバランスも当然のことです。
当院でも、他院修正や眼瞼挙筋機能のない先天性眼瞼下垂のケースを除いて、通常の後天性眼瞼下垂症であれば、概ね3ヶ月経った時点で再手術のリスクは、5%程度だとご説明さえていただいております。
眼瞼下垂症を専門としてることもあり、私自身、他医療機関様のHPを拝見することが多いのですが、HPは宣伝目的の要素がどうしても目についてしまいます。
どうしても、眼瞼下垂症を手術で治せば、ハッピーになれるというニュアンスにしてしまいがちです。
術前の説明が足らず、結果として、手術を受けられる患者様のご理解が不足された状態で、手術を行ってしまうと、術後に様々なトラブル的な症状について、質問の嵐を受けてしまうような状況になります。
今回のブログ記事は、出来るだけ、眼瞼下垂症手術の術後において考えられる要素を網羅して書かせていただいたつもりです。
(もちろん、書ききれなかった事柄についても、どんどん加筆をしていくつもりです・・・)
大抵のトラブルは、術後の腫れに伴うものなので、ある程度のダウンタイムを経過すれば、消失するものなのですが、先に述べさせていただいたように、不幸ながら再手術になることもあります。
私個人のスタンスとしては、後出しをせず、先出しの説明を心がけていれば、初回手術で上手くいかず、再手術になったとしても、きちんと説明・リカバリー出来れば、信用・信頼を失うことは少ないと考えております。
もちろん、初回の手術で上手くいくことが1番の結果であることには変わりませんが・・・・
したがって、当院では、懇切、丁寧な術前カウンセリングに力を入れると同時に、遠方の方でなければ、出来るだけ、細かく通っていただいて、術後の管理をしっかり行うようにしております。
遠方の方でも、メール、LINEチャットシステムなどでIT技術使って、遠隔でも、最大限対応できるようにしております。
もちろん、手術の成功率を上げる努力を欠かさないようにし、最高の眼瞼下垂症手術がご提供できるように今後も工夫を重ねていきたいと思っております。
目に関する悩みで困ったら、まずは専門医に相談してみてください。
「目が開けにくくなった」「まぶたが瞳にかかって視界が狭い」「眠そうと言われる」 そんなお悩み、放っておかずに一度ご相談ください。
当院への眼瞼下垂症手術のご相談は、LINEから簡単にご予約いただけます。
医師または専門スタッフが、あなたの症状に合わせてご案内いたします。








