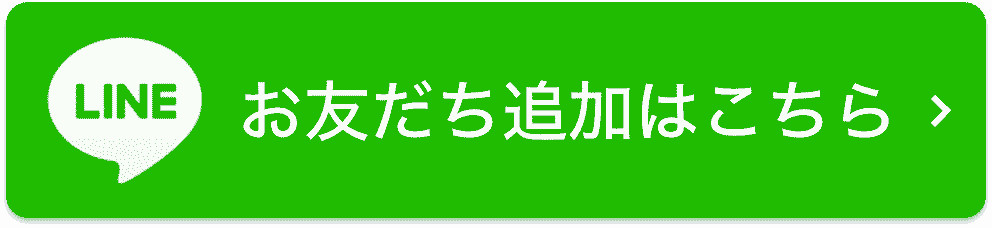網膜静脈分枝閉塞症について

網膜静脈分枝閉塞症とは
網膜静脈分枝閉塞症は、網膜(眼球の内側に張り巡らされている薄い神経の膜)にある静脈という血管が閉塞し(詰まって)、突然、血液が流れなくなってしまう状態になることです。
網膜は大変薄い組織なため、網膜内の動脈と静脈が交叉する部分では血管の1番外側の壁を共有(交叉)しています。
この交叉部分の動脈に動脈硬化が起きていると、静脈もその影響を受けて閉塞してしまいます。
静脈が詰まると、網膜の血管が広がったり、蛇行したり、行き場を失った血液があふれ出して出血(眼底出血)したりします。
または、網膜に血液中の水分がたまり網膜に浮腫み(網膜浮腫)を起こすこともあります。
症状
主な自覚症状として、眼底出血では瞳孔から入ってくる光を網膜で受け取ることができなくなるため、視力が低下したり、飛蚊症(視界に黒いものが浮遊して見える症状)が生じたりします。
網膜浮腫では視力の低下や視界の歪みを自覚します。
特に黄斑(網膜の中心にある視力に最も影響を及ぼす場所)に出血や浮腫みがある場合は、視力低下や視界の歪みを極端に感じるでしょう。
症状は一般的に、静脈の閉塞部位が視神経乳頭に近いほど重く、逆に閉塞部が末端の静脈で、出血の範囲が狭ければ自覚症状が全くないこともあります。
眼底出血は時間をかけて引いていきますが、その後の視力の回復の度合いは黄斑の障害の程度によって異なります。
黄斑浮腫の程度が高度な場合は網膜の機能が失われたまま、視力が回復しないことも少なくありません。
網膜静脈分枝閉塞症が発症しやすい人
網膜静脈分枝閉塞症は、一般的には50歳以上の年配の方に起こりやすいと言われています。
また下記の持病を持っている方は発症の確率が高くなります。
①高血圧
高血圧によって、網膜の血管に負担がかかり傷められるため(動脈硬化)。
②糖尿病
血液の流れが悪くなり、血管が詰まりやすくなるため。
こういった持病をお持ちの方は、症状が無くとも年に1回は眼底検査の定期検診をおすすめ致します。
上記に記したように一般的には年配の方に多く発症する病気ではありますが、若い人が発症することが全くないわけではありません。
若い方では血管自体の炎症や全身の病気(全身性エリテマトーデスなど)が原因で発症することもあります。
網膜静脈分枝閉塞症の治療
治療としては、発症した直後(急性期)には、閉塞した血管に血流を再開させるための薬物投与の処置がとられることがあります。
血管強化薬や網膜循環改善薬などが主に用いられます。
またこれに引き続き、黄斑浮腫が認められる場合や、血流の途絶えた網膜の面積が大きい場合、新生血管(網膜静脈分枝閉塞症発症後に新しくできる脆い血管)の発生が認めれる場合などには下記の治療が必要になります。
治療は主に下記の3つの治療法が柱となります。
①眼球への薬物注射
抗VEGF薬を直接眼球に注射する方法です。
血流が不足すると、そこに新しい血管を作るように促すVEGFというサイトカイン(生理活性物質)が産生されます。
この物質には血管壁から血液成分を漏れやすくする作用もあるため、黄斑浮腫の原因になると考えられます。
このVEGFの働きを抑制する抗VEGF薬を眼球に注射することで黄斑浮腫の改善などが望めます。
またこの薬は浮腫に対して即効性があり、患者様の負担が少ないというのが利点になります。
ただしこの薬の効果は数か月(病気の重症度によります)でなくなってしまうため、一旦改善しても、高い頻度で浮腫などの病気の悪化が再発します。
浮腫の再発を避けるためには長期間経過を観察し、浮腫の再発が認められれば追加投与が必要になります。
②レーザー光凝固術
これは、静脈閉塞により、血流が途絶えてしまった網膜に向けてレーザー光を照射し、網膜を凝固する治療です。
レーザーを照射することで、血流不足の網膜がVEGFという物質(黄斑浮腫や新生血管の発生を促す物質)を産生するのを抑制します。その結果、黄斑浮腫が改善したり、新生血管の発生を抑制します。
しかし網膜の血流障害や浮腫の程度が強いとその効果は弱くなります。
レーザー光凝固術を行うと、「視界が暗くなったり、狭くなる」という副作用が生じることがあります。
そういったことから、レーザー光凝固術は、前記の薬物治療だけでは十分な効果がない場合に行います。
③硝子体手術
硝子体は眼球内部の大部分を占める無色透明の柔らかな組織です。
網膜静脈分枝閉塞症発症後しばらくして、発生してしまった新生血管が破裂したりすると、硝子体内出血で埋め尽くされて、視力が著しく低下してしまいます。
手術で、この硝子体と出血を除去することで、視力が改善します。
硝子体出血が軽度の場合は、手術をしなくても、1-2か月間程度で自然に出血が吸収されて視力が改善することもあります。
硝子体手術は、出血量が多く、視力が著しく低下している場合に検討されます。
網膜静脈分枝閉塞症の合併症
網膜静脈分枝閉塞症では症状が落ち着いた頃(慢性期)になってからも合併症が起きることがあります。
下記によくある合併症を3つご紹介します。
①硝子体出血
静脈閉塞した部位から下流は血流が途絶えてしまい、網膜は無血管野(血流が存在しない部分)となります。
無血管野ではVEGFという物質が産生されます。VEGFは、新しい血管の新生を促し、それによって新生血管(本来は存在しない新しくできた血管)が発生します。
新生血管の血管壁は大変もろく破れやすいために容易に出血が起こります。
新生血管からの出血は硝子体内に広がり、硝子体が濁って視力が低下します。これを硝子体出血と呼び、重症の場合、前述のように手術治療を行います。
新生血管は、網膜の無血管野が広いほど発生頻度が高くなります。
そのため、前述したように無血管野をレーザーで凝固する治療を行い新生血管の発生を抑える治療を行うこともあります。
②血管新生緑内障
新生血管は、網膜だけでなく眼球内の他の部位に発生することもあります。
眼球内は、絶えず新たに液体(房水)が産生され、また、その房水は吸収されています。この仕組みで、丸い眼球の形が保たれています。
房水の吸収は、眼球内の隅角という場所で行われています。
新生血管が隅角で発生してしまうと、この房水の流出口が塞がってしまいます。そして房水が眼球内に蓄積することで眼圧(目の中の圧力)が上昇します。
血管新生緑内障は、眼圧が高くなることで視神経が圧迫され、視野が狭くなったり、ときに失明することもある病気です。症状は急激に進行することがあります。
主な自覚症状は、視界が狭くなる・視力低下・眼の奥の痛みなどになります。
③網膜剥離
網膜が眼底から剥がれてその部分の視力が障害される病気です。
網膜で発生した新生血管は、硝子体へと伸びていきます。この伸びた新生血管が網膜を引っ張り、網膜に裂孔(穴が開くこと)ができたり、剥がれたりします。
また、新生血管から漏れ出たタンパク質や血液により、眼球内で増殖膜という膜が形成され、この膜が網膜を引っ張って裂孔(穴が開くこと)ができたり、剥がれたりすることもあります。
裂孔ができると網膜の裏側へ眼球内部にある水分が流れ込み剥離部分は急速に拡大していきます。
剥離した細胞は短時間で機能を失ってしまうため早急に手術を施行する必要があります。
まとめ
このように網膜静脈分枝閉塞症は、眼球内に多くの悪影響を及ぼします。治療で最も大切なことはできるだけ早期に治療を開始することです。
幸いにして視力が維持できた場合にも、その後の合併症で取り返しのつかない事態を招いてしまうこともあります。
そのような事態を避けるために、大切な視力を守るために、定期的な眼科検診を受けることに加え、持病をお持ちの方は内科で血圧、血糖値、コレステロール値の管理をして頂くが重要な鍵となります。
定期検査では眼底を医師が観察します。検査自体は患者様の侵襲度は低いものになります。
眼底を観察するために光を瞳孔に当てます。光を当てると瞳孔は自然と小さくなってしまいます。網膜の隅々まで観察するため検査の前に点眼薬(散瞳薬)を使用します。
散瞳薬を点眼してから15分から30分で瞳孔が大きくなり検査が可能な状態になります。点眼の効果により、ピントが合わせづらくなりかすんで見える様な状況になります。
検査後は点眼の効果が一般的に3時間から4時間程度続きますが徐々に回復していきます。
網膜静脈分枝閉塞症は片眼に発症することの多く、普段は両眼で見ているので発症したことに気が付かないこともあります。
合併症を未然に防ぐためにも継続的な定期検診は欠かさなようにしましょう。