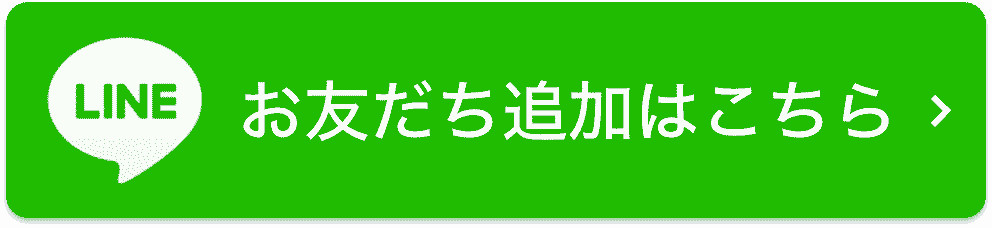眼瞼下垂の手術「挙筋腱膜前転法」
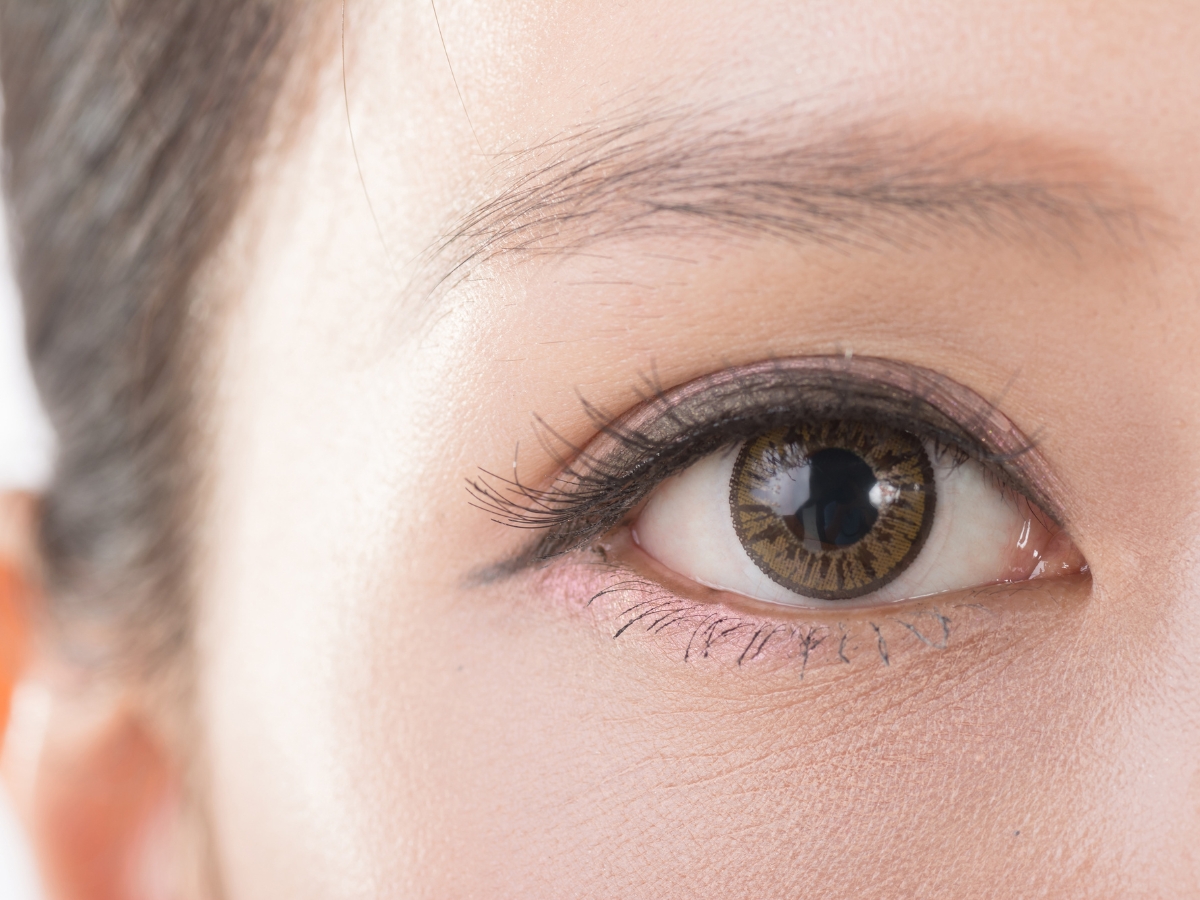
眼瞼下垂の手術について
「眼瞼下垂(がんけんかすい)」の治療法のなかで、「眼瞼挙筋(がんけんきょきん)」がゆるんでしまって「瞼板(けんばん)」を上げる力が弱まった状態のときに行われるのが「挙筋腱膜前転法(きょきんけんまくぜんてんほう)」です。
まぶたがしっかり上がるためには、この眼瞼挙筋と瞼板がしっかりと付着している必要があります。
ところが、何らかの原因によって眼瞼挙筋と瞼板を介する挙筋腱膜が、延びたり緩んだりしてしまうと、まぶたを上げる力が弱まってしまうのです。
そこで、挙筋腱膜前転法は、挙筋腱膜を瞼板に再固定することで、まぶたを上げる力を取り戻すことを目的として行われます。
この手術のほかに、「眼瞼挙筋(がんけんきょきん)」の機能が残されている場合に実施される「挙筋短縮術」と、眼瞼挙筋がほとんど機能していない際に実施される「前頭筋吊り上げ術」の2の手術方法があります。
改めて基本用語をチェックすると、眼瞼挙筋はまぶたを上げる(開ける)ときに大きな力になる筋肉。
瞼板は、まぶたの先端に付いてまぶたを引き上げる役割を担う板状の軟骨、挙筋腱膜は、この瞼板につながる組織を指します。
このほか、まぶたを上げる(開ける)際に補佐的に働くミュラー筋を縫い縮める「ミュラー筋タッキング術」などを行う医院もありますが、 当院としては、ミュラー筋を眼瞼下垂症手術において、術後眼瞼痙攣(眼瞼けいれん)を引き起こす可能性もあり、避けるべきだと考えております。
眼瞼挙筋腱膜前転術とは?
手術の手順としては、一般的には、局所麻酔を行なってから、皮膚・眼輪筋の切開切除から始まり、次に「眼窩脂肪(がんかしぼう)」を包んでいる薄い膜である「眼窩隔膜(がんかかくまく)」の切開へと進み、眼瞼挙筋腱膜の前面を露出させます。
麻酔が正常に効いていれば手術中の痛みはそれほどありません。
TKD切開法では、自然な幅狭の二重ラインを作る基本となる切開です。
余剰皮膚を全く取らない施設もありますが、日本人は皮膚が余っているケースが殆どですので、切除する方が自然な術後デザインとなります。

眼瞼挙筋腱膜を傷つけないように、丁寧に露出させる。

切開後は、挙筋腱膜を確認して適正な位置まで前に引き出し(前転)、挙筋腱膜を瞼板に縫い合わせて再度、固定します。
当然、眼窩脂肪と眼瞼挙筋腱膜との接着組織(ファシア)を剥がすことは非常に大事だと当院は考えております。
(ファシアリリース法)

皮膚縫合

この手術方法は、ミュラー筋などの筋肉を傷つけるリスクを減らすことができるため、安全性が高く負担を最小限にする手術といわれています。
ただ、まぶたの切開を伴いますので腫れを避けることができず、1週間から10日前後まで、ダウンタイム(手術してから回復するまでの期間)が長引くことがあります。