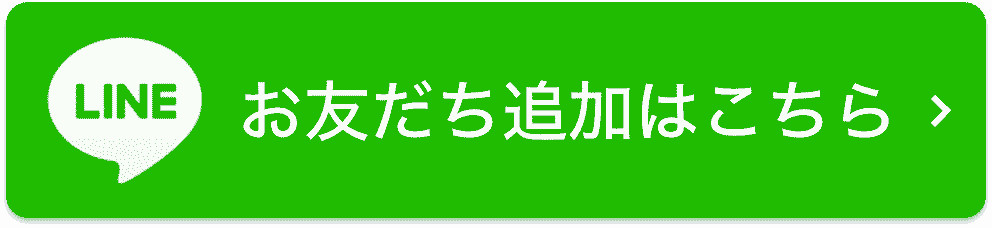どのように効く?緑内障に使われる治療薬:点眼薬(目薬)、内服薬(飲み薬)を詳しく解説します。

緑内障という病気をご存知でしょうか?

緑内障とは、眼圧(眼球を球体として維持するための圧力)によって、視神経が押し潰されることで障害を受け、結果として、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。
そして、一度、障害を受けた視神経は、現代の医学では元の状態に戻すことは難しいので、非常に怖い疾患であると言えます。
しかも、この緑内障は、40歳以上の5%が発症しているともいわれている病気で、高齢化が著しい日本では緑内障になっている方は年々増えています。
正気のうちは、全くと言っていいほど自覚症状が少ないため、緑内障の発症に気づかず、治療をしていない方も多いと言えるのですが、緑内障は放っておくと視野が狭くなり、最悪の場合には目が見えなくなること(失明すること)があるので早期に発見して治療をすることが非常に重要です。
そして、糖尿病網膜症を抜いて、緑内障が中途失明の原因の第一位となったことは有名な話です。
緑内障の治療の目標は、適正な眼圧にコントロールすることです。
病的な眼圧により視神経にダメージが与えるられるため、視神経に負担をかけないように眼圧を適正な範囲に保つことが求められます。
現在では、様々な緑内障の治療薬が開発されていて患者さんの状態に応じて治療薬が選択され使用されております。
緑内障の治療は、生涯続くことを前提としているので継続するために病気や治療薬を理解することが重要です。
そこで、今回は緑内障の治療薬について解説していきます。
緑内障とは

緑内障とは、何らかの原因(主に眼圧)で視神経が障害されることで視野が狭くなってしまう病気のことです。
一度狭くなってしまった視野を元に戻すことができないため、病気が進行してしまうと、最悪の場合には失明に至ることも少なくない病気です。
目の痛み、かすみなどの自覚症状が末期になるまで少ないので未治療で過ごしている方も多いので早期発見して治療することが重要な病気です。
(実際、多くの患者さんは別の症状で眼科を受診して偶然緑内障が発見されることが多いです。)
先に述べた通り、高齢化により患者数も増加して視覚障害の原因としても第一位です。
緑内障は、眼球内を循環する房水という液体が何らかの原因でうまく排出することができず、眼圧が上昇して視神経が圧迫されて障害されることで起きると考えられています。
そのため、眼圧を十分に下げることで視野が改善し、緑内障の進行を抑制ができます。
眼圧を下降させるためには薬物(点眼,内服,点滴),レーザー,手術の3つの選択肢がありますが,原則的には点眼治療が第一選択となります。
当院において、緑内障の治療(眼圧下降方法)としてよく用いられるのが以下になります。
SLT(緑内障のレーザー治療)
点眼薬・内服薬・点滴
いずれにしても眼圧を下げる効果があり、当院では、治療薬処方に加えて、日帰りSLT(緑内障レーザー手術)を積極的に多数施行しております。

緑内障治療薬の役目
今回は「緑内障の治療薬」についてお話したいと思います。
緑内障の治療薬において、眼圧を下げる作用を持った点眼薬が一般的には第一選択として使用されます。
しかしながら、その種類は非常に多く、「どのような種類の目薬があるのか」、「それぞれの効果や副作用はどのようなものがあるのか」についての理解は非常に難しい状態だと思います。
今回は、緑内障の治療薬についてスポットを当てて、解説したいと思います。
緑内障の治療を進める上で、それらについての知識を持つことは非常に重要と言えます。
このブログ記事では、緑内障の治療で使用される治療薬の種類、それぞれの効果、そして副作用について詳しく解説します。

眼球は、例えていうなら、源泉掛け流し温泉のように、少しずつ温泉水を供給しながら、溢れた水が排水されて、一定の量の水が溜まっている状態です。

温泉水の湯口に当たるのが、毛様体と呼ばれる部分であり、排水溝の入り口が隅角にある線維柱帯となっております。
つまり、房水は、毛様体で作られており、そして、その毛様体から角膜の端にある隅角にあるフィルターである線維柱帯を通って、シュレム管に集まり、静脈に流れ出します。
そして、緑内障の治療薬は、この房水の循環に作用するものが殆どです。
緑内障の治療薬とは、眼球内の房水を減らす薬のこと、眼圧を下げる作用のある薬となるわけです。
緑内障の治療薬

緑内障の治療薬は、非常にたくさんの種類がありますが、総じて、眼圧の上昇の原因である房水が生成されないようにするか、排出しやすくして眼圧を下げる効果を持っています。

したがって、緑内障の目薬の種類はたくさん種類がありますが、作用機序ごとに分けると、
このように点眼薬は作用機序の違いによって分類され、状況に応じて複数の点眼薬を併用することがあります。
こちらでは、緑内障治療薬の分類を一つずつ、ご紹介します。

プロスタグランジン関連薬(FP2受容体作動薬・EP2受容体作動薬)
当院で取り扱う主なプロスタグランジン製剤
後発医薬品(ジェネリック)があるものは※で一般名を表示しています。
プロスタグランジン関連薬 :FP2受容体作動薬

房水流出路には
- 主経路(経線維柱帯流出路)
- 副経路(経ぶどう膜強膜流出路)
の2つがあります。
プロスタグランジン作動薬(PG製剤)は副経路(経ぶどう膜強膜流出路)からの房水量を増加させます。
プロスタグランジン作動薬の中でも、FP2受容体作動薬は、緑内障治療において、第一選択薬と言っていいぐらい最もよく使用される点眼薬の一つです。
作用機序
プロスタグランジン作動薬は、プロスタグランジンF2αのアナログであり、眼内のシュレム管を通じた副経路(経ぶどう膜強膜流出路)を改善します。
具体的には、この薬剤は眼内の線維柱帯の細胞に作用し、細胞間のスペースを広げることで房水の流出を促進します。
結果として、眼圧が低下し、緑内障による視神経の損傷していくリスクが減少すると言えます。
FP2受容体作動薬の利点
- 高い効果: プロスタグランジン作動薬は、他の緑内障治療薬と比較して眼圧を大幅に下げることができます。
- 使用の便利さ: 多くのプロスタグランジン作動薬は1日1回の投与で済むため、患者の負担が少なく、治療のコンプライアンスが高いと言えます。
※コンプラアンスが高いというのは、忘れずに、キチンと点眼が出来るという意味です。
以下は、緑内障治療において一般的に使用されるプロスタグランジン作動薬の一覧表です。
| 一般名(成分名) | 商品名 | 特徴 | 投与 頻度 |
|---|---|---|---|
| ラタノプロスト | キサラタン | 眼圧を効果的に下げ、1日1回の投与で済む | 1日1回 |
| トラボプロスト | トラバタン | 強力な眼圧降下効果を持ち、1日1回の投与で良好な眼圧コントロールが可能 | 1日1回 |
| ビマトプロスト | ルミガン | 眼圧降下効果が高く、他の治療薬でコントロールが難しい場合にも使用される | 1日1回 |
| タフルプロスト | タプロス | 保存料不使用のオプションがあり、保存料に敏感な患者に適している | 1日1回 |
| ラタノプロストエノプロスト酸エステル | レスキュラ | ラタノプロストのプロドラッグであり、眼圧降下効果に加えて、保存料が不要な製剤もある | 1日2回 |
FP2受容体作動薬の副作用
これらの薬剤は、眼圧を下げることによって緑内障の進行を遅らせることができますが、副作用が発生する可能性もあります。
具体的には、眼の周りが黒ずんできたり、睫毛が太く長くなってきたり、瞼(まぶた)が下がってきたり(眼瞼下垂)、上瞼のあたりがくぼんできたり(上眼瞼溝深化)と眼の周りに起きる副作用が多いです
これら、PG関連薬(FP2受容体作動薬)の特有の眼周囲の副作用をPAP (Prostaglandin-associated periorbitopathy) といい、いちばん副作用の出現リスクの少ないキサラタン®でも、1年で約10%の確率で発症します。
これらの副作用は通常軽度であり、治療の中断を必要とすることは少ないですが、患者によっては気になる場合があります。
このPAPによる外見上の変化に注意しながら、眼科医は、診察において、毎回確認しております。

PG関連薬(FP2受容体作動薬)に特徴的な副作用として色素沈着があります。
色素沈着は、皮膚に点眼薬が付着したまま放置すると目の周りが黒ずんでしまうことです。
そのため、お風呂に入る前に点眼するなどの対策が必要です。
プロスタグランジン関連薬 :EP2受容体作動薬

房水の流出には主に2つの経路があり、ひとつは線維柱帯を通ってシュレム管に入り上強膜静脈から眼外へ排出される線維柱帯流出路(主経路)です。
もうひとつは虹彩根部及び毛様体筋を経て上毛様体腔及び上脈絡膜腔に入り、強膜から眼外へ排出されるぶどう膜強膜流出路(副経路)となります。
体内のプロスタノイド受容体は、房水流出に深く関わると言われております。
その中の一つであるEP2受容体刺激作用により、主経路(経線維柱帯流出路)及びぶ副経路(経ぶどう膜強膜流出路)を介した房水流出が促進され、眼圧が下がります。
つまり、2018年に発売されたオミデネパグ イソプロピル(エイベリス)は、各種プロスタノイド受容体の中でもEP2受容体を選択的に刺激して眼圧降下作用を発揮する日本で開発された薬剤です。
既存の薬剤と異なり、選択的にEP2受容体を刺激し、主経路(経線維柱帯流出路)および副経路(経ぶどう膜強膜流出路)の両方からの房水流出を促進することで眼圧降下の効果があります。
利点と禁忌
- 眼圧の効果的な低下: EP2受容体作動薬(エイベリス)は、FP2受容体作動薬と同等程度に眼圧を効果的に下げることができる。
- 副作用のリスクが低い: 他のプロスタグランジン類似薬剤と比較して、EP2受容体作動薬は副作用のリスクが低いので、安心して使用できる。
既存のプロスタグランジン関連薬と比べて目の周りが黒くなりにくいなどの利点もありますが、白内障手術後の患者さんには使えず、一部のFP2受容体作動薬と併用できないという欠点もあります。
交感神経β遮断薬
交感神経遮断薬

房水が作られないようにして、排出をしやすくするお薬です。
交感神経遮断薬は交感神経が刺激されないようにスイッチである受容体に蓋をするイメージの薬剤です。
緑内障治療薬ではβ遮断薬とα1遮断薬が使用されます。
β遮断薬は、房水が作られる部位に作用して房水が作られないようにします。

α1遮断薬では、毛様体筋を弛緩させてブドウ膜強膜流出路と呼ばれる房水排出路を広げて房水流出量を増やします。
β遮断薬の中には、喘息を誘発させる薬剤もあるので喘息がある方は事前に医師に相談する必要があります。
αβ遮断薬、α受容体とβ受容体両方を遮断します。
交感神経遮断薬による緑内障治療の点眼薬は、主にβ-アドレナリン受容体遮断薬(βブロッカー)であり、α1遮断薬、αβ遮断薬は使われなくなっております。
作用機序
βブロッカーの点眼薬は、房水の産生を減少させます。
具体的には、眼の毛様体に存在するβ-アドレナリン受容体を遮断することで、房水の生成を抑制し、結果として眼圧を下げます。
日本で発売されている交感神経遮断薬の緑内障治療点眼薬
以下は、日本で利用可能な主なβブロッカー系緑内障治療用点眼薬の一覧です。
| 薬剤名 | 一般名(成分名) | 特徴 |
|---|---|---|
| ・チモプトール ・リズモン | チモロールマレイン酸塩 | チモプトールXEとリズモンTGは薬の効果が持続する1日1回タイプの点眼薬となっている。 本剤の成分(チモロール)とプロスタグランジン関連薬との配合剤(ザラカム配合点眼液 など)がある。 本剤の成分(チモロール)と炭酸脱水酵素阻害薬との配合剤(コソプト配合点眼液 など)がある。 本剤の成分(チモロール)とα2刺激薬との配合剤(アイベータ配合点眼液)がある。 |
| ミケラン | カルテオロール塩酸塩 | 1日1回タイプの剤形(ミケランLA点眼液)がある。 本剤の成分(カルテオロール)とプラスタグランジン関連薬(ラタノプロスト)の配合剤(ミケルナ配合点眼液)がある。 |
| ハイパジール | ニプラジロール | β遮断作用以外に眼房水の排泄を促進させるα1遮断という作用も持つ。 最近では、ほとんど使われることがない薬剤です。 |
βブロッカー点眼薬は、点眼薬ではあるが、全身に対する副作用も稀におこり、死亡例の報告もあります。
気管支収縮作用や心血管系の副作用があらわれる可能性があるので、注意が必要です。
炭酸脱水酵素阻害薬

炭酸脱水酵素阻害薬は緑内障治療において使用される薬剤で、炭酸脱水酵素という酵素を阻害することで眼内の房水産生を減少させることにより眼圧を下げます。
作用機序
炭酸脱水酵素阻害薬は、毛様体に存在する炭酸脱水酵素の活動を抑制します。
この酵素は、二酸化炭素と水から炭酸イオンと水素イオンを生成し、これが房水の生成に関与しています。
酵素の活動を抑制することで、房水の生成が減少し、結果的に眼圧が下がります。
炭酸脱水酵素阻害薬は点眼薬と内服薬の2つの形態で処方されますが、それぞれに特徴があります。
点眼薬:炭酸脱水酵素阻害薬
点眼薬形態の炭酸脱水酵素阻害薬は、直接眼に投与され、局所的に眼圧を下げる効果があります。
内服と違い点眼薬の利点は、全身への影響が少なく、副作用が局所的に限定されることです。
炭酸脱水酵素阻害薬の点眼薬の主な副作用には、眼の刺激感や不快感がありますが、これらは通常軽度であり、問題になることは非常に少ないです。
利点と欠点
- 利点: 炭酸脱水酵素阻害薬は、特に急性の緑内障発作において迅速に眼圧を下げる必要がある場合に有効です。
点眼薬は局所的に作用するため、全身的な副作用が少ない。 - 欠点: 経口薬は全身的な副作用が発生する可能性があり、しびれ感、疲労感、胃腸の不快感、頻尿などが報告されています。点眼薬でも眼の刺激や不快感が生じることがあります。
一般的な点眼薬の炭酸脱水酵素阻害薬
| 一般名(成分名) | 商品名の例 | 特徴 | 投与頻度 |
|---|---|---|---|
| ドルゾラミド | トルソプト | 局所的に眼圧を下げる効果があり、一日2〜3回の投与が一般的。 | 1日2〜3回 |
| ブリンゾラミド | アゾプト | ドルゾラミドと同様に局所的に眼圧を下げる。一日2〜3回の投与。 | 1日2〜3回 |
内服薬(ダイアモックス):炭酸脱水酵素阻害薬

経口薬形態の炭酸脱水酵素阻害薬(ダイヤモックス)は、全身に作用し、特に急性の緑内障発作や、他の治療法でコントロールできない高眼圧を迅速に下げる必要がある場合に使用されます。
経口薬の主な欠点は、全身的な副作用のリスクが高まることです。
副作用には、しびれ感、疲労感、胃腸の不快感、頻尿などが含まれます。
| 一般名(成分名) | 商品名の例 | 特徴 | 投与頻度 |
|---|---|---|---|
| アセタゾラミド | ダイアモックス | 急性の緑内障発作に対する治療や長期治療に使用される。全身的な副作用に注意が必要。 | 医師の指示に従う |
緑内障治療における炭酸脱水酵素阻害薬の使用は、患者の状態や他の持病、使用中の他の薬剤との相互作用を考慮して、慎重に決定し処方されます。
点眼薬よりも副作用の頻度が増えますが、経口薬はより迅速な眼圧の低下が必要な場合に選択されることが多いです。
交感神経α₂刺激薬
交感神経作動薬/アドレナリンα2受容体作動薬(商品名 アイファガンなど)

交感神経を働かせるためのスイッチである受容体には大きく分けてα受容体とβ受容体が存在し、緑内障の交感神経作動薬にはα2作動薬などがあります。
眼球で房水が作られる部位に存在しているα2受容体が刺激されることで房水が作られないようにしたり、ブドウ膜強膜流出路からの房水流出を促進します。
したがって、アイファガン点眼薬(一般名:ブリモニジン酒石酸塩)の作用機序は、主に以下の二つの方法によって眼圧を下げる効果を発揮します。
1. 房水の産生抑制
アイファガンは、眼内での房水の産生を抑制します。
房水は眼球内の圧力を維持するために重要な液体ですが、その産生量が多すぎると眼圧が上昇し、緑内障のリスクが高まります。
アイファガンに含まれるブリモニジンは、アドレナリンα2受容体作動薬として作用し、房水の産生を減少させることで眼圧を下げる効果があります。
2. 房水の流出促進
アイファガン(ブリモニジン)は、眼内の房水の流出を促進することも眼圧を下げるメカニズムの一つです。
房水の適切な排出が妨げられると、眼内圧が上昇し、緑内障を引き起こす原因となります。
アイファガン(ブリモニジン)は、房水のうち特に眼房前房からの流出を促進することで、眼圧の正常化に寄与します。
Rhoキナーゼ阻害薬
Rhoキナーゼ阻害薬 (商品名 グラナテック)

Rhoキナーゼは平滑筋細胞の収縮,各種細胞の形態制御など,種々の生理機能の情報伝達に関与する低分子G蛋白の1つである。
例えば血管平滑筋細胞なら,Rhoキナーゼを阻害すると血管弛緩の方向に働くことになる。
Rhoキナーゼ阻害薬は線維柱帯細胞の形態の変化→細胞外マトリクスの変化→シュレム管内皮細胞の接着への作用によって,線維柱帯→シュレム管を介する主流出路からの房水流出を促進して眼圧を下降させることができます。
Rhoキナーゼ阻害薬は、緑内障や高眼圧症の治療において比較的新しいクラスの薬剤です。これらの薬剤は、Rhoキナーゼ経路を阻害することにより、眼内の房水流出を改善し、眼圧を下げる効果があります。
効果
Rhoキナーゼ阻害薬の主な効果は、眼圧の低下です。これは、以下のメカニズムによって達成されます。
- 房水流出の改善: Rhoキナーゼ経路の阻害は、眼内のトラベキュラーメッシュワーク(房水の主要な流出経路)内の細胞と細胞間基質の構造を変化させます。これにより、房水の流出が促進され、眼圧が低下します。
- ぶどう膜強膜流出路の促進: 一部の研究では、Rhoキナーゼ阻害薬がぶどう膜強膜流出路(別の房水流出経路)を通じた房水の流出も促進する可能性が示唆されています。
副作用
Rhoキナーゼ阻害薬は一般によく耐容されますが、いくつかの副作用が報告されています。これらの副作用は主に局所的なものであり、以下のような症状が含まれます。
- 結膜充血: 最も一般的な副作用の一つで、使用後に眼が赤くなることがあります。
- 眼の刺激感: 点眼後に一時的な刺激感や不快感を感じることがあります。
- 角膜の変化: 角膜表面の微細な沈着物やぼやけた視界が報告されていますが、これらは通常一時的なものです。
- 眼瞼の皮膚反応: 使用部位の皮膚に軽度の反応が生じることがあります。
治療における位置づけ
Rhoキナーゼ阻害薬は、他の眼圧降下薬と併用されることが多く、特に従来の治療が効果不十分な場合や、追加の眼圧降下が必要な場合に選択されます。
これらの薬剤は、緑内障治療における新しい治療オプションとして注目されており、特に房水流出経路の異なるメカニズムを通じて眼圧を下げる能力が評価されています。
副交感神経作動薬
副交感神経作動薬(商品名 サンピロなど)

サンピロ点眼液は、有効成分としてピロカルピン塩酸塩を含む点眼薬です。ピロカルピンは副交感神経作動薬に分類されます。
副交感神経が刺激されることで毛様体筋と呼ばれる部位が収縮して線維柱帯という房水の排出口が広げられ、排出しやすくなるので眼圧が下げられます。
閉塞隅角緑内障は,虹彩が隅角へ引き上げられるか,または押し上げられるかのいずれかの要因により、隅角が狭くなり,房水排出が物理的に妨げられて眼圧が上昇する状態です。
結果として、眼圧上昇により視神経が障害される。
中でも、急性緑内障発作は、視力障害が急激に進行し,永久に持続する恐れがあるため,直ちに治療を開始しなければならない状態であり、一度に複数の薬物を投与することになります。
そして、副交感神経作動薬(サンピロ)は、瞳孔を縮瞳させる作用から、急性緑内障発作により散大した瞳孔を小さくさせ、眼圧を下げることが期待できるため、使われることが多い。
欠点
実は、ほとんどの緑内障は狭隅角緑内障ではなく、開放隅角緑内障なので、急性発作は起こりません。
そして、副交感神経作動薬(サンピロ)は、隅角を広げる作用であるため、開放隅角緑内障において眼圧下降効果が期待できないとも言えます。
結果として、今では、副交感神経作動薬(サンピロ)は使われなくなってきました。
毛様体筋が収縮すると瞳が縮むので副作用としては一時的に視界が見えづらくることがあります。
作用機序
- 副交感神経支配の筋肉への作用: サンピロは副交感神経支配の筋肉、特に瞳孔括約筋と毛様体筋に直接作用します。これにより、これらの筋肉が収縮し、縮瞳(瞳孔の縮小)を引き起こします。
- 房水の流出促進: 毛様体筋の収縮により、房水の流出経路が改善され、眼内の房水の流出が促進されます。これにより眼圧が低下します。
効果
- 緑内障治療: サンピロは、閉塞隅角緑内障の治療に用いられることが多いです。
- 検査後の縮瞳: 眼科における散瞳検査後に開いてしまった瞳孔を元の大きさに戻すためにも使用されます。
緑内障点眼薬の多剤併用について
緑内障の治療において、薬剤の多剤併用は一般的なアプローチとも言えます。
これは、単一の薬剤では十分な眼圧の低下が得られない場合や、異なる作用機序を持つ薬剤を組み合わせることで治療効果を高めるために行われます。
ただ、緑内障の点眼薬は長期間にわたって点眼を続ける必要があり、どの種類の薬剤も長期間点眼することで、充血したり、角膜の表面が荒れてきたりすることがあります。
さらに言えば、各点眼薬には、それぞれ特徴的な副作用があったりし、むやみやたらに多く使えば良いというわけでもありません。
つまり、多剤併用には副作用のリスクや、防腐剤による眼の表面への影響などを考慮し、点眼薬を選択することが必要となってきます。
防腐剤について
BAK(ベンザルコニウムクロライド)は、その強力な抗菌作用により、点眼薬の中で細菌の増殖を防ぐ役割を果たします。
多くの点眼薬には、このBAK(ベンザルコニウムクロライド)が防腐剤として含まれており、眼の表面、特に角膜や結膜に対して刺激性があります。
そして、BAKが長期間にわたって使用していると、眼の表面(特に角膜や結膜)に損傷を与えることがあります。
しかも、緑内障は、何種類も点眼薬を重ねることが多いため、このBAKによる防腐剤アレルギーによる角膜表面(オキュラーサーフィス)の問題が出やすいと言えます。
緑内障を使用していて、原因不明の角膜表面トラブルが出る場合には、防腐剤フリーの緑内障治療薬に切り替えると良くなるケースがあります。
もちろん、防腐剤フリーの緑内障点眼薬は、ドライアイや角膜の感受性が高い患者に推奨されることがあります。
BAKフリー点眼薬の重要性

BAKフリー点眼薬は、BAKなどの防腐剤を含まない点眼薬を指します。
特に、ドライアイ、角膜感受性の低下、アレルギー性結膜炎などの眼の表面疾患を持つ患者や、長期間にわたって複数の点眼薬を使用する緑内障患者にとって、BAKフリー点眼薬は重要です。
BAKフリー点眼薬の利点
- 眼の表面への刺激の低減: BAKフリー点眼薬は、眼の表面への刺激が少なく、特に敏感な眼やドライアイの患者に適しています。
- 治療の遵守の向上: 点眼薬による不快感や副作用が少ないため、患者の治療遵守が向上する可能性があります。
- 眼の表面疾患のリスク低減: 長期間の使用による眼の表面疾患のリスクが低減されます。
BAKフリー点眼薬の問題点
- 保存性: 防腐剤を含まないため、BAKフリー点眼薬は開封後の保存期間が短く、細菌汚染のリスクが高まる可能性があります。そのため、使用期限や保存方法に注意が必要です。
- コスト: BAKフリー点眼薬は、製造や包装に特別な配慮が必要なため、従来の点眼薬に比べてコストが高くなることがあります。
合剤の利用
眼圧を下げる効果が最も高く、比較的副作用の少ないプロスタグランジン関連薬が緑内障治療薬の中心になってきていますが、眼圧を十分に下げることができない場合には複数の点眼薬を使用していきます。
- 点眼間隔を5分以上空けるという時間をなくなりこと
- 点眼薬の数が減り、点眼の忘れを防ぐことができること
- 単剤を別々に服用することよりも価格が安くなること
点眼薬を同時に使用すると薬液があふれてしまうので点眼してから別の点眼薬を使用する時には5分待つ必要があります。
複数の点眼薬を使用するためには時間が必要であり、手間に感じることも多いです。
複数の点眼薬を一つの薬剤にまとめることで点眼した後に待つ手間を減らすことができるので治療を継続しやすいメリットが有ります。
お薬の価格も単剤を別々に使用することよりも価格が安くなることのメリットもあります。
しかし、複数の点眼薬を使用すると副作用が起きる可能性も高くなるので配合剤が最初から使用されることは少ないです。
それでも、合剤は、患者の利便性を高め、治療の遵守を向上させることができます。また、防腐剤の全体的な曝露量を減らすこともできます。
副作用の面からの点眼処方の工夫
- 治療の遵守を考慮: 患者が日常的に複数の点眼薬を使用するのが難しい場合、合剤の処方を検討します。
- 防腐剤の影響を最小限に: 長期治療が必要な患者には、可能であれば防腐剤フリーの製品を選択します。
- 副作用のモニタリング: 患者を定期的にフォローアップし、副作用の兆候を監視します。副作用が見られる場合は、薬剤の変更や治療計画の調整を検討します。
代表的な合剤の例
以下は、緑内障治療における日本で保険診療で処方可能な合剤の一覧表です。これらの合剤は、異なる作用機序を持つ薬剤を組み合わせることで、眼圧を効果的に低下させ、患者さんの利便性を高めることが期待できます。
緑内障治療の合剤一覧表
| 合剤の種類 | 成分 | 商品名 | 特徴 | 用法 |
|---|---|---|---|---|
| PG + β | ラタノプロスト + ティモロール | ザラカム、ドルモロール | プロスタグランジン類似薬とβブロッカーの組み合わせで眼圧を効果的に低下させる。 | 1日1回点眼 |
| PG + β | ラタノプロスト + カルテオロール | ミケルナ | カルテオロールは選択的β1ブロッカーで、心臓への影響が少ない。 | 1日1回点眼 |
| PG + β | トラボプロスト + ティモロール | デュオトラバ | トラボプロストは強力なプロスタグランジン類似薬で、ティモロールとの組み合わせで眼圧低下効果が高まる。 | 1日1回点眼 |
| PG + β | タフルプロスト + ティモロール | タプコム | タフルプロストは保存料フリーのオプションがあり、敏感な眼にも適している。 | 1日1回点眼 |
| CAI + β | ドルゾラミド + ティモロール | コソプト | 炭酸脱水酵素阻害薬とβブロッカーの組み合わせで眼圧を効果的に低下させる。 | 1日2回点眼 |
| CAI + β | ブリンゾラミド + ティモロール | アゾルガ | アゾルガはコソプトよりも眼の刺激が少ないのだが、ドロっとして、逆に、差し心地が悪く感じる場合がある。 | 1日2回点眼 |
| α2 + Rhoキナーゼ | ブリモニジン + ネタルサミド | グラアルファ | α2アドレナリン作動薬とRhoキナーゼ阻害薬の組み合わせで眼圧を効果的に低下させる。 | 1日2回点眼 |
| α2 + β | ブリモニジン + ティモロール | アイベータ | α2アドレナリン作動薬とβブロッカーの組み合わせで眼圧を効果的に低下させる。 | 1日2回点眼 |
| α2 + CAI | ブリモニジン + ブリンゾラミド | アイラミド | α2アドレナリン作動薬と炭酸脱水酵素阻害薬の組み合わせで眼圧を効果的に低下させる。 | 1日2回点眼 |
緑内障治療薬の副作用の判断するポイント
緑内障治療に使用される点眼薬は、眼圧を下げることで視神経の損傷を防ぎ、視野の喪失を遅らせる効果があります。しかし、これらの薬剤は副作用を引き起こす可能性があり、患者さんやその家族がこれらの副作用を認識し、適切に対処することが重要です。
緑内障は、末期になるまで症状を感じることが少ないので副作用が出る可能性もある点眼薬を使うことに疑問を感じ、面倒に感じる方も多いでしょう。
しかし、緑内障の治療で点眼薬は最も重要な治療法なので、疑問に感じたことや気になることは担当医に相談した上で継続して点眼薬を使ってください。
緑内障点眼薬の使用に注意が必要な方
点眼薬には副作用が少ないというイメージがありますが、医薬品であるために副作用も存在しています。
特に緑内障の点眼薬には目だけでなく全身に副作用が起きてしまうこともあります。
例えば、緑内障点眼薬の中には喘息を誘発するものや心臓の動きを活発化させて高血圧や頻脈などを起こす点眼薬もあるので持病のある方は事前に相談したほうがいいでしょう。
その他にも、眼科以外の診療科で出されるお薬に中には、眼圧を上げてしまう医薬品も存在します。
緑内障の種類によっては抗パーキンソン病薬や狭心症治療薬など一部の医薬品の使用ができないこともあります。
他に使用している医薬品がある場合には医師に相談してください。
副作用と判断すべき状態のポイント
- 眼の赤みや刺激感: 点眼薬によっては結膜充血や刺激感を引き起こすことがあります。
- 視覚の変化: ぼやけた視界や視野の変化が生じる場合があります。
- 眼の痛みや不快感: 点眼後に痛みや強い不快感を感じることがあります。
- 眼瞼の変化: 眼瞼の腫れ、かゆみ、色素沈着などの変化が見られることがあります。
- アレルギー反応: 発疹、かゆみ、重度の腫れなど、アレルギー反応の兆候が見られる場合があります。
対策
- 副作用の症状が軽度の場合: 症状が軽度で、日常生活に大きな支障がない場合は、しばらく様子を見ても良い場合があります。しかし、症状が持続する場合は医師に相談してください。
- 副作用の症状が重度の場合: 視覚に影響が出る、痛みが強い、アレルギー反応の兆候がある場合は、直ちに医師の診察を受ける必要があります。
緑内障治療薬と副作用の表
| 緑内障治療薬の種類 | 一般的な副作用 | 症状 |
|---|---|---|
| プロスタグランジン類似薬 | 結膜充血、睫毛の成長、眼の色素沈着 | 眼の赤み、まつ毛の異常な長さや密度、虹彩の色の変化 |
| βブロッカー | 呼吸困難、心拍数の低下 | 呼吸の苦しさ、脈拍の遅さ |
| αアゴニスト | 口の乾燥、眠気 | 口の渇き、日中の過度の眠気 |
| 炭酸脱水酵素阻害薬 | 手足のしびれ、味覚の変化 | 手足のピリピリ感、食べ物の味が変わる |
| Rhoキナーゼ阻害薬 | 結膜充血、角膜の沈着物 | 眼の赤み、視界のぼやけ |
副作用が発生した場合は、使用している点眼薬の名前と症状を正確に医師に伝えることが重要です。
医師は症状に応じて、治療計画の調整や別の薬剤への変更を検討することがあります。
自己判断で治療を中断したり、薬剤の使用方法を変更したりすることは避け、必ず医療専門家の指示に従ってください。
緑内障の方でも使える市販の目薬の選び方
緑内障は,視神経と視野に特徴的変化を有し,通常,眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患であり,隅角所見により「開放隅角緑内障」と「閉塞隅角緑内障」に大別されます。
このうち,抗コリン作用により緑内障の悪化又は急性緑内障発作の発症が生じうるのは「閉塞隅角緑内障」のみと考えられております。
したがって、開放性(開放隅角緑内障)はもちろんのこと,閉塞性(閉塞隅角緑内障)を含め,ほとんどの緑内障症例に対して抗コリン薬を使用することは問題になりません。
特に白内障手術を既に受けている症例であれば基本的に問題はありません。
抗コリン薬の使用が問題になるのは,閉塞隅角緑内障および原発閉塞隅角症(緑内障性視神経障害を起こしていない原発閉塞隅角緑内障の前駆状態)の症例で,白内障手術をまだ受けておらず,さらにレーザー虹彩切開術などの治療も受けていない症例と,一部の特殊な重症例のみです。
一方で、一般用医薬品においても,かぜ薬,鼻炎用内服薬,胃腸薬,鎮暈薬など,抗コリン作用を有する成分が配合されています。
そのため,添付文書の「使用上の注意」の「相談すること」の項に「緑内障」が記載されているものについて,緑内障患者から相談を受けた際は,緑内障の病型を可能な限り確認するとともに,確認が取れない場合や緑内障の病型が不明である場合は担当医師に相談してください。
このような時には担当医へ
目薬も医薬品なので必ず副作用があります。目の刺激感、かゆみ、充血やかすみなどはよくある副作用としてありますが、目以外にも症状が起きることもあります。
・めまい
・動悸
・息切れ
・喘息
このような症状や気になることがあれば担当医や薬剤師に相談してください。
まとめ
緑内障は、自覚症状が少ないので緑内障であることに気づかずに治療をしていない人も多い病気です。
症状が進行すると視野が狭くなり失った視野をもとに戻すこともできずに最悪の場合には失明することもある病気です。
そのため、緑内障は早期発見、早期治療が必要な病気です。
近年では、様々な緑内障の治療薬が開発され、自分にあった治療薬を使用することで緑内障の進行を抑えることができます。
緑内障の治療は生涯続きますので定期的な検査と継続的な点眼治療が重要です。
よく病気のことを理解してじっくり治療に取り組む必要があるので気になることや疑問点があれば担当医と相談してください。